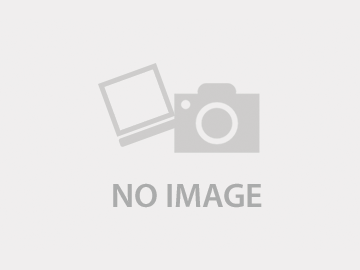王安石と北一輝二人に共通するところは、改革者であるがゆえに、条件的客観的評価システムをクリアしたものによって強固に構築されたグループ主義の主観的に捻じ曲げられた批判・中傷を受け続けたことです。
初期の条件的客観的評価システムである科挙を本格的に導入した北宋では経済の拡大により、大地主・大商人が官僚機構と繋がって台頭し、自作農・小商人が没落して彼らに隷属するような構造が出来上がっていきます。
税負担者の減少、経済の硬直化に加えて、官僚群と軍隊は増加の一途を辿り、財政破綻の危機になります。
その中で改革の必要性を説いたのが王安石です。
貧農や小商人に対し低融資で支援する青苗法・市易法
大商人の暴利を防ぎ、かつ財政収入確保の効率化のための均輸法
農民にとって大きな負担となっていた労役を免ずる募役法
貴族・特権官僚・大地主などの特権・利益を抑え、中小農民や中小商工業者を保護・育成し、財政の再建を図ろうとした政策に加え、官僚機構を改革するための科挙改革である三舎法・倉法なども時の皇帝である神宗に上奉します。
それまでの科挙の最重要項目は文化人としての素養つまり詩文の才能などであったために実際に役人として重要であった法知識や経済能力は問われませんでした。
そのためにそれらに長けたものを雇い、実務を執らせていました。
それがで胥吏です。
しかし、彼らは無給のために手数料や民衆から搾取によって収入を得ており、その搾取はかなり悪辣なものでありました。
そこで王安石は科挙において現実政治に対する実践を図る論文試験を重視するようにして、官僚に法律・経済に対する知識を持たせる一方で、実務を取り仕切っていた胥吏の腐敗を防止するために、俸給を支給する代わりに賄賂を取れは厳罰に処す倉法を制定します。
加えて、三舎法により大学を創設し、実際の政治に必要な知識を教育によって身に付かさせ、外舎・内舎・上舎の三段階に分けた定数600、200、100の中で年2回の試験を通過した者が上に登り、上舎での成績優秀者が官僚として採用されるようにしていきます。
新法の改革によって、国庫には潤沢な資金が入り、その資金を市易法の低率融資や雇用対策費用に充てて徴税層に還流させることで景気が上がり、治安も改善されました。
国家財政の好転と政治の安定化を承けて、複雑な二重官制を一元化し、官僚機構の煩雑性の改善・人件費削減という国初からの懸念は解決に向かいました。
しかし神宗が崩御すると、旧法党の司馬光が宰相となり新法は悉く廃止されてしまいます。
安定した民主的コントロールがない時は頼れるのは名君のみです。
名君であった神宗の時は改革は進行しましたが、暗君の時は逆行してしまいます。
暗君といわれる徽宗が皇帝の時代に新法が政権を握りますが、神宗期の新法は国家財政の健全化のために用意られましたが、徽宗はそれを自らの奢侈のために用いました。
集めた国の公的資金を絵画購入や石集めなどの私的な趣味に散財し、それでも資金が足りないとなると皇帝の威光を悪用して、民間から大量の賄賂やお目こぼし料を取るようになりました。
宰相や地主・商人・役人達も新法を私腹を肥やす道具として勝手に利用し始めます。
青苗法や市易法では、官人・大商人・胥吏らが偽っ青苗銭や市易銭を借り受け、それを貧農や小商人に対して貸し付けるということが公然と行われ、方田均税法では、担当役人らの独断で、従来のものより短い尺を使って算出されるという不法な測量が行われ、余剰の土地と判定したものを強制的に没収し、役人への賄賂までが要求されました。
また募役法が免除されるはずの土地でも役税の徴収が勝手に行われ、保甲法の役も賃金が支払われずに差役化が進行し、国家整備の法である農田水利法も、農村から花石綱などの宝物を運ぶために一度しか利用しない道路を建設するなど意味のない工事が乱発されるといった有様でした。
統制の取れなくなった北宋の社会は破滅に向かって行きます。
地主官僚の支配体制の強化・固定化が進んだその後の明や清の時代において、王安石は伝統を破壊し、国を滅亡に追いやった極悪人とされます。
新法党と旧法党の争いによって国力が低下して、北宋滅亡の原因になったとされ、悪人官僚の代表と評価されることになります。
しかし、儒教の影響が強い政治では朋党の争いが付きものであることは、どの時代・どの国であっても共通することは歴史が証明しており、同じ北宋の時代でも新法以前の 慶暦の党議に見られるように時の政権に対して反対派が党派を組んで批判を行うことがしばしばあって、そのために改革がほとんど実現することはありませんでした。
その行動を擁護する目的に書かれたのが欧陽脩の朋党論ですが、現実の北宋の政治においての朋党間の政治対立は反対派を小人の朋党として非難・追放することに終始し、政治的混乱を招くことになり、特別それは新法・旧法の争いに限定されることではありませんでした。
歴史を少し調べればすぐにわかる事柄でありながら、王安石は北宋滅亡の原因として間違った解釈の下、最悪の政治家として清末期まで800年近くの間において非難され続きます。
特に明代には、王安石は新法の悪政を施行したから悪人なのではなくて、元来悪人だから悪政をしたのであるとまで罵倒されます。
王安石の新法は、近代多くの国で行われた社会経済政策の先駆けを成した観があります。
科挙官僚を中心とす大地主・大商人=(イコール)近代風に言えば財閥の利権の構造を改革する王安石の新法には猛烈な反対があり、特権階級・貴族階級の閨閥の頂点に立つ皇后は皇帝に向かって泣きながら新法の中止を求めたエピソードも残っています。
王安石はたちまち奸臣とされてしまい、皇帝神宗の支持がなければ、失脚どころか生命まで失しなった可能性が高かったと思われます。
神宗は名君であったこともありますが、国政に最終的責任を負わなくてはならない立場である以上、周りに非難されても王安石を支持するしかなかったとも言えます。そうしなければ国民からの支持を失い、非難されるだけでなく、最悪皇帝の地位を失うことになるからです。
靖康の変における徽宗皇帝のようにです。
北宋滅亡から800年、旧来の科挙官僚を中心とする地主官僚支配体制が続く限り、王安石の表立っての味方は誰一人もいませんでした。
王安石の科挙改革、倉法、三舎法も北宋時代に撤廃されました。
しかし、近代の西欧において、科挙制度を手本にしながら、王安石の改革的要素も含む、より優れた条件的評価システムであるメリットシステム(詳しくは⑶グループ主義を制御する客観的評価システムの種類と長所・欠点を参照して下さい。) やそのメリットシステムにより生まれた官僚機構コントロールする民主主義から派生した結果的客観的評価システム(詳しくは⑹民主主義と客観的評価システムの関係を参照してください。)により国力を増大させた英国などの西欧列強国の圧力の中で、旧体制の変革が必要不可欠と差し迫った段階において、やっと王安石は再評価されるようになります。
変法運動の理論家である梁啓超など数多くの学者たちは旧来の価値観をかなぐり捨てて王安石を賞賛するようになります 。
この様なことは、当然のことながら、科挙と同じ条件的客観的評価システムであるメリットシステムにも性質上起こる可能性が高く、戦前の日本における北一輝がまさに、北宋における王安石に当たるともいえます。
戦前の日本においても、軍部・大蔵省、内務省などの近代官僚を中心とする大地主・財閥の利権構造が出来上がっていきます。
安定した民主主義から派生する結果的客観的評価システムがあれば、それらの構造の形成を阻害したり、制御したりしていきますが、国民主権でなく、天皇主権を本旨とする大日本帝国憲法の性質上かつ国民の天皇ではなく、天皇の国民とした天皇絶対の神格化した戦前教育などにより、実権は首相ではなく、天皇の取り巻きにあり、安定した民主主義から派性する結果的客観的評価システムの構築は不可能な状態でした。
結果的客観的評価システムの裏打ちのない民主主義は、古代アテネ、共和制ローマ、近代のワイマール共和国時代のドイツの様に、民主主義の欠点である金権政治や衆愚政治のみが強調されてしまって、衰退・崩壊してしまうことは歴史が物語っています。
戦前の日本の近代官僚機構も天皇の取り巻きを取り込み、政官財癒着の強固なグループ主義を構築し、公益を侵食する形で増大し、暴走していきます。
民主主義自身から派性し、グループ主義から公益を守る重要な機能を果たすことにより、民主主義自身を安定に導くところの結果的客観的評価システムは、天皇の地位・権限が至高絶大で大日本帝国憲法における天皇の権限ははさながら絶対君主のものであったために構築されず、また絶対君主制における公益を背負い、責任を問われる立場にある天皇も『君臨すれども統治せず』を原則として、権限と判断を取り巻きに委ねられる方針が代々取られていたことから、強固なグループ主義を掣肘するものが、民主主義という面から見ても、絶対君主という面から、両方の面から見ても存在しませんでした。
つまり、どっちつかずの為に、公益をグループ主義から守るコントロール性という点では最悪といえる状態にあったのです。
そのために戦前の日本において、特に、民主主義・資本主義のマイナス面と言える要素が重なった憲政の常道期、昭和大恐慌の時期においては、現代における格差社会と言われる生易しいものではなく、著しい不公平が罷り通り、娘の身売り・子供の間引きに象徴される農山漁村の窮乏、小商工業者の疲労が蓄積される中、その悲惨な状況下に政治家は無為無策で、財閥と私腹を肥やし、官僚機構を中心とした政官財癒着のグループ主義が公益を侵食する暴走を続けていきます。
その強固なグループ主義に真向から立ち向かい、現実的かつ建設的な政策を提言していく者が現れます。
それが北一輝です。
北は天皇を神聖視せず、万世一系は未開国の思想としながら、共産党の様に打倒対象と考えず、天皇は国民に近い家族の様な存在という戦後の象徴天皇制に類似する国民の天皇という考え方を二十歳にして新聞にて発表します。
すぐに連載が中止しとなりますが、北はその後の著作においてもその考え方を曲げることなく、発禁処分を受け続けます。
当時の天皇の国民とした天皇制を容認していた美濃部達吉や吉野作造と比べても民主主義的であり、美濃部達吉の天皇機関説よりも北一輝の考え方の方が戦後の象徴天皇制に近いといえます。
逸早く、基本的人権の尊重、貴族院・華族制廃止などの階級制度の無用論、言論の自由、農地改革、財閥解体、女性の人権保護を唱え、また共産党と違い私有財産・宗教の自由も認めており、まさに戦後民主主義の雛形と言えるものでした。
しかし、戦前の天皇主権と中途半端な民主主義の間を上手く利用して、増大した近代官僚機構を中心とした政官財の癒着構造体にとって、北は既得権益を侵す、許すことができない存在として強く憎まれます。
戦後も軍部に全ての責任を押し付けることによって生き残った君側の奸である宮中グループをはじめ旧支配層の多くが生き延び、官僚組織はそのまま温存されたため、北一輝は戦前戦後から現代まで、百年に渡って、王安石の様に不当に非難され続けられます。
戦前のファシズム体制下では民主主義者として、戦後民主主義体制下ではファシズムの象徴として黒を白、白を黒とする様なご都合主義の矛盾した非難ありきの非難がされていきます。
戦前において、2,26事件の首謀者として処刑されますが、青年将校の証言からも北は直接行動には反対で、それを常に抑止する立場にあったため、この事件においても全く部外者的な状態にありました。
日本改造法案大綱に触発されて2,26事件が起こったという思想的影響においても、改造法案を信奉していた青年将校は磯部浅一を含め少数派でした。
その磯部の証言に『大多数の青年将校は北や改造法案から思想的な影響すら受けてない』と他の同士の改造法案の思想の不徹底さに憤慨するのも残っています。
また、田中勝中尉の『自分は北らの思想に染まって、民主革命を成さんとしたものではありません』という証言などを見ると、どの方向性から見ても、主犯とするには無理があります。
民間人を担当していた吉田裁判長も『北一輝は2,26事件に直接責任がないので不起訴ないし軽刑』と主張していました。
しかし、寺内陸相が『北は極刑にすべきである。北は証拠の有無に関わらず、黒幕である』と極刑の判決を強要します。
不当な判決に対して、北は真の黒幕である皇道派の重鎮が皆、青年将校を見限って責任逃れをする中で、はしごをはずされ、行き場の失った青年将校の大義の受皿になるため、逆らうことなく、青年将校に殉ずる形で受け入れます。
そればかりか、冤罪で国賊として死刑宣告されている身でありながら、『たとえ、三ヶ月でも良いから、ここから出してくれたら、中国に渡り、蒋介石政権と日本の間の話をつけてこられるのだが…その後で、私は戻って来て死刑になるよ。それができないのが心残りである』と最後まで公益を考えて亡くなります。
北は昭和七年に『対外国策に関する建白書』で、「日米戦争は必ず英米露支対日本の戦争つまり世界全体とする戦争となるから、これをしてはならない」と戒め、、三年後の日米合同対支財団の提議の建白書では、日米戦争は支那を問題とする形で勃発すると予言しています。
その対策に2,26事件直前は北は事件に関与するどころか、辛亥革命時の盟友である張群が蒋介石政権の外交部長の地位に就いていたことから、日中和解に自ら乗り出さんと重光外務次官とも長時間協議し、広田外相や代議士の永井柳太郎とも渡支の時期について相談して、三月の予定にしていました。
直前になって、青年将校が決起することを伝えられた北は内心では時期ではなく、国際間の調整より始めるべきかと思い、その行動に困惑しつつも、かれらへの情宜を捨てられず、同意を与え、事件の収拾策としての真崎大将に一任の助言(真崎大将に一任させれば青年将校をむざむざ犠牲にすることはあるまいと考えての助言だったそうですが、真崎大将は青年将校を切り捨てていきます。)などをしていきます。
それらに関する責任を北は重く考え、青年将校に殉じていきます。
なぜ、現実主義者であった北が青年将校に殉じたのか?
それは青年将校の純真さにあったと思われます。
彼らのほとんどはエリートコースである陸大出がおらず、中には意識的に拒否して、立身出世コースから外れた者も多くいました。東北の惨憺たる事態、食べるものがなく、三百戸の農家から二百人の娘が売られていく窮状を憂え、純真ならではの社会を変えなければならないという切羽詰まった危機意識が動機の中心に位置付けられていました。
そのような皇道派の隊付きの将校を中心とするものに対して、エリートの陸大出が多い、いわゆる天保銭組といわれた幕僚将校が多い統制派は政官財の癒着の中心に位置していました。
前者が一君万民の家族主義的国家イメージであり、後者がナチス的国家社会主義的国家イメージでありました。
統制派が出した陸軍パンフレットの内容には『戦いは創造の父、文化の母』であると書かれ、尽忠報国の精神に徹底し、国家の生成発展のため、自己滅却の精神を育み、国家を無視する国際主義・個人主義・自由主義思想を排除し、真に挙国一致の精神に統一することなど、まさに軍国主義・ファシズム的なものでした。
日本改造法案の言論の自由、基本的人権の尊重、刑事被告人の人権保障、被告が無罪となった際の国家賠償制度の確立、治安維持法の廃止、普通選挙、象徴天皇制、近隣諸国の権利の重視、個性の伸張を力説した個人主義、障害者・児童・労働者など社会的弱者への権利保護・援助などの内容とはまさに正反対の内容でした。
北自身、陸パンの内容は財閥と妥協せる国家社会主義的色彩濃厚で、自身の改造法案の内容が一向に察知できなかったと述べています。
陸軍内部では皇道派は現場叩き上げ、統制派は高級官僚の事務エリートとされていますが、統制派はかねてより皇道派の軍事クーデター勃発を誘導させ、その鎮圧過程を逆手にとり、自分達の国家社会主義的ファシズム体制を確立させようとカウンタークーデターの構想を練っていました。
2,26事件の二年前に作成された対策要綱にそれは見て取れます。
2,26事件の青年将校であった安藤大尉の遺書にも、『自分達を犠牲に、虐殺して、自分達の行動を利用して、軍部独裁のファッショ的改革がなされようとしている。逆賊の汚名の下に虐殺され、これでは死に切れない。』と書かれています。
これらには宮中グループの木戸幸一なども絡んでおり、事件の一ヶ月前には既に既成事項として情報は回っており、元老の西園寺公望も前もって避難していました。
その後、陸軍統制派は事件処理に名を借りて、着々と軍部独裁のファシズム体制を確立していきます。
しかし、そのファシズム体制は連合国によって倒されます。
そして、改造法案に沿った戦後民主主義改革が行われますが、戦前においてファシズム体制に反する民主主義者として処刑された北は戦後において、なぜか再評価されるどころか、ファシズムの教祖とされてしまいます。
統制派が組み立てたファシズムと北の改造法案の類似点を敢えて探したとしても、対外政策おけることと資本の国家による干渉か又は規制位ですが、それらであっても質的には全く異なるものでした。
改造法案の対外政策を先ず見ていくと、『植民地であった朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできないが、国民としての地位は平等でなければならず、政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が実施される、将来獲得する領土についても文化水準によって民族に関わらず市民権を保証する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範になることができる。』というものでした。
当時の帝国主義万能の時代、ほとんど国が植民地支配を受けるか、さもなくば植民地支配をするかの時代でした。
第二次世界大戦後、脱植民地化が世界的に進行した時点での視点で見ると、独立を認めないことだけでも、帝国主義的・ファシズム的に見られるかもせれませんが、当時の弱肉強食の時代、弱者の国となると、人口が半減する程に搾取されたり、ホロコーストを受けたりするのが、決して珍しくない時代の視点で見ると全く変わって来ます。
陸軍パンフレットをほとんどの新聞が賛成し、穏健的、民本主義者で植民地国に同情的と見られていた吉野作造でさえ、朝鮮独立を認めておらず、日本の中国における権益を固守すべきで、日本が中国に出した二十一ヶ条要求に対しても賛成するような状態で、それに反する者は非国民と責められる様な時代でもありました。
その状況下でも、北は二十一ヶ条要求を鋭く批判し、日本に来ていた中国の革命派の譚人鳳を大隈重信と会見させて、彼らの見解を直接日本政府に伝えるための援助をしています。
また北の改造法案は朝鮮の独立を公言してはいませんでしたが、朝鮮の独立を希求する人々にとって、朝鮮の独立問題を曲がりなりにも採り上げている、ほとんど唯一の思想でもありました。
北は日韓の合併という本来的な趣旨に照らして、この合併は韓国併合でも併呑でもなく、対等の合併であるべきと主張しています。
そして、朝鮮は日本の属邦、植民地ではなく、その地位は内地と平等でなければならず、日本内地と同一なる行政法の下に置き、日本の一行政区として北海道と等しく西海道とせねばならないとしています。
その上で、現下の朝鮮政策を『甚だしく英国の植民政策を模倣したるが故に、根本精神からして日韓合併の天道に反するものであり、東洋拓殖会社が英国の東インド会社の統治を真似て植民地経営したり、日本の資本家が官憲と結託して土地財産を奪い民衆の生活を不安に陥れ、その不満を憲兵政治で抑えたりすることがまさに悪模倣にある。』と指摘します。
『日本が行うべきことは父兄的愛情をもって、朝鮮民族の覚醒的成長を促進すること』で、具体案として『十年後より地方自治制を実施して参政権の運用に慣習せしめ、二十年後に完全に日本人と同じ参政権を与える』としています。
朝鮮人の中には戦前の日本で朝鮮独立問題をまともに考慮してくれていたのは、ただ北一輝がいただけという思いを持っている者もおり、関東大震災の折の朝鮮人虐殺事件の時、独立運動家の朴烈が北の所に逃げ込み、助けを請うということがあり、北はここも監視されいて危ないからと、当座のお金を渡し、朴を逃がしています。
このことから窺われるのは、北は朝鮮の独立闘争に同情していたということを日本の当局や朴烈ら朝鮮人が知っていたということです。
戦後も、こうした心理はしばらく引き継がれ、在日朝鮮人の中には、関東大震災の様な出来事が起きたら、北一輝の様な人物の所に隠れようと、但し、現在にも北一輝の様な人物がいると仮定すればだがという言動も残されています。
また、中国に対しても、北は中国人以上に中国の立場を考慮・行動し、中国の利権を日米ソに次々に切り売りしている孫文を売国奴とまで批判し、辛亥革命の孫文と並ぶ両巨頭の一人である宋教仁が、清朝政府に利することになったとしても中国の主権・領土を守るために、間島問題における国境交渉に積極的に介入し、寄与したことについては逆に大きく評価しています。
北一輝は、中国における民主革命である辛亥革命に命を懸けて支援し、宋教仁の唯一無二の理解者で親友でもありました。
また、辛亥革命の重鎮であった譚人鳳の孫を大輝と命名、養子とし、溺愛します。大輝の母は産褥熱で亡くなり、父は反北京政府の活動で獄に繋がれ、脱獄を試みて銃殺されました。
一年二か月の赤ん坊は病弱のために骨と皮ばかりに痩せ衰え、この世のものとは思えなかった状態でした。
譚人鳳は日華両国のため、東洋永遠平和のために彼を養育してほしいと頼み込み、北は引き受けます。
その他にも辛亥革命の若き運動家の面倒をよく見、その中の一人に2,26事件時、中華民国外交部長であった張群がいます。
張群は北を頼って日本に亡命して来た一人で、北の墓の揮毫者でもあります。
戦後、中華民国(台湾)の代表として国賓待遇で来日した時は、北一輝夫人の住んでいる貧民窟を訪ね、北の位牌に線香を手向けています。
当時の時代の視点で見ると北は日本全国民の平均値よりはるかに非帝国主義的であり、石橋湛山の存在を考えると最も非帝国主義的とは言えなくとも、かなり非帝国主義的であり、当時の置かれている帝国主義的な環境下で、理想主義でなく、現実主義的な物差しで見ると、最も非帝国主義的と言えるかもしれません。
そもそも、北が改造法案を執筆した背景には、五・四運動の全支那に渦巻く排日運動の鬨の声が鳴り響く状況下にあり、原案が書かれたのも日本ではなく、上海でした。
北の中国における命懸けの活動の目的は英露を中心とする植民地化・分割政策から中国を守り、独立を目指す勢力を援助することにありました。
しかし、中国で日本の帝国主義的な対中政策を身をもって実感した北は、天皇の取り巻きである重臣・官僚・財閥・軍閥の複合体こそが日本の民主主義革命並びに中国革命の進展に立ちはだかる反動勢力であり、これらを打倒し、侵略と経済的略奪を行わずに、他国の民主革命を支援できる民主国家に日本がなり、植民地大国となっているイギリス・ロシアとの軍事的対決も辞さない日本を創ることが必要不可欠と考えていました。
帝国主義的大国であるイギリス・ロシアによって不当に抑圧されている外国の民族を開放する為に戦い、領土を取得することを北は主張しています。
但し、新領土では土着人を指令官として行政に当たらせるべきとし、西欧列強のような収奪主義的な統治でなく、民族に関わらず、人権を保障し、人種主義を廃して、諸民族の平等主義の理念を確立して、世界平和の規範を打ち出さなければならないとしています。
北が意図していたのは、古代ローマの最盛期、五賢帝時代のように、属州出身が皇帝になったり、近代イギリスの内地においてのスコットランド人が自由に栄達し、イギリス帝国はスコットランド帝国と呼んだ方が正確だと言われる程に活躍したような寛容と公平の実践であり、日本改造法案の改革つまり、日本の戦後民主改革のような改革を浸透させながら、地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認めていくというものであり、イギリスがカナダに対して行った対等のパートナー的対応と類似しています。
イギリスが世界の覇権国と成れたのは、スコットランド、カナダなどの白人人口が多数を占める国に対してはグループ主義(この場合は民族主義)に流されることなく、公平性と寛容の精神によって統治したことが大きな要因であり、覇権国から転落した要因の大きなものの一つとして、非白人植民地に対してはグループ主義(民族主義)に流されてしまって、不公平と不寛容の種を播いてしまったことがあります。
北は世界の全ての異なる民族にも公平と寛容の原則によって行くべしという思想であり、日本が世界の王者となるべきとしたのも、非白人国に対して西欧列強が従来的に行った搾取的圧政をもってなるべしとしたのではなく、寛容と公平の原則により成長して戦後は民主政治の普及を前面にパクス・アメリカーナによって、イギリスと入れ替わり、世界の覇権国になったアメリカ的なものに少し類似点があるといえます。(但し、戦後、アメリカはしばらくの間は日本の戦後民主化を助け、その成功を持って、韓国や台湾にも農地改革などを進行させようとし、イランにおいても当初は民主化を強化し、モサデクを支援し、イランが国力をつける方向性に誘導しようと、建前上と同じ行動を取っていましたが、アイゼンハワー政権においてダレス兄弟が影響力を持つことによって、方向性は一変し、 多国籍企業が一人勝ちする、資本主義放任主義から生まれた帝国主義を彷彿とさせる新植民地主義的政策にシフトチェンジして行きます。)
実際的に世界的な西欧列強に対しての脱植民地化や日本の戦前体制から戦後民主主義体制への変換は両方とも武力的アプローチが必要であったことは歴史が証明していますが、吉野作造より八年早く普通選挙論を著作で中核的議論にし、普選論の先駆の一人であり、民主主義者であった北が民主的革命や武力によって西欧列強に対抗していくことを合理化していくようになったのも現実主義者たる由縁だったと思われます。
戦後、脱植民地化が進んだのも、北一輝や宮崎滔天の様な日本人が多数、命を省みず、経済的・軍事的にも支援したことが大きく関与しており、極めつけは望ましくない戦争で、統制派が指揮した帝国主義的な戦争であったにしろ、西欧列強を追い出し、また日本も敗戦を迎えたことによる植民地支配の空白状態を利用しての今まで多数の日本人によって支援され、準備された原住民の独自の軍隊による独立戦争が引き起こされたことが大きく、それによって西欧列強も経済的利益が保てなく撤退して行くことになります。
ここで初めて、石橋湛山の植民地経営は経済的に合わないとする理論が適合することになりますが、それはあくまで武力的アプローチが介在した上で成立したものと言えます。
戦前日本の支配層には二つのグループがあったとされます。
一つは重臣などを中心とする宮中グループで、もう一つは統制派による軍閥グループです。
両方とも、帝国主義的路線であることは違いはなく、前者は英米追随の中国を分割して植民地支配をしていく路線で、後者は単独で中国を支配していく路線でした。
前者が戦後、権力温存のために後者を切り、自分達を正当化しましたが、実質、両グループは路線面での対立はあっても深く結合していました。
ファシズムの定義として、独占資本と独裁指向が挙げられますが、北は天皇主権から国民主権を目指し、財閥規制を指向したことから、全くその定義に合わず、宮中グループや統制派は、独占資本である財閥と一体化し、天皇主権ながら天皇には原則として政治的発言を控えさせ、自分達の独裁状態を実質、構築したことで、まさにファシストの定義そのものとなります。
明治維新には二つの流れがあり、一つは吉田松陰に代表される精神派で、絶対的権限を持つ天皇を中心とした仕組みを作り出すという考え方です。
もう一つは横井小楠、勝海舟、坂本龍馬に代表される近代派で天皇を制限君主として立憲君主制の下で近代民主国家を組み立てて行くという考え方です。
近代派は、暗殺されたり、権力の中心から外れたりして行き、実権を握るのは、天皇に対しては近代派的考え方を押し付け、国民に対しては精神派的考え方を押し付けることによって権限を自由に掌握していくグループです。
彼らは売国的に、国民から出た莫大な資金で注ぎこんだ官営物を驚く程の安値で財閥に売り渡し、その財閥と姻戚関係を結び、癒着したグループ主義を構築していきます。
結果的客観的評価システムや公益に責任を問われる君主の管理もない状態で、これらのグループ主義を止める手段はなく、悪貨が良貨を駆逐していくように、貪官汚吏が出世し、良史を駆逐し、また出世した者も、自然の流れで自らの権力を維持するために、グループ主義の流れに沿った行動をしていきます。
近代派が創り出した大きな公益の果実をグループ主義がもぎ取り、自らの功績としながら、せっかくのシステムを歪め、腐敗させていきます。
代表的な人物として井上馨がいます。賄賂と利権で私腹を肥やし、西郷隆盛からは井上は政府高官ながら三井の大番頭だと非難されています。
悪質な尾去沢銅山の汚職事件を司法卿の江藤新平に追及され辞職しても、伊藤博文のコネで復帰しますが、常に汚職・不正疑惑の噂が常に付き纏います。
山県有朋も有名な山城屋和助事件を起こしています。
当時の陸軍省の一割弱にも及ぶ巨大な公金を勝手に貸し付け、賄賂を得ています。
また同様に三谷三九郎事件では、不正に陸軍省の公金を貸し付ける似た汚職事件を起こしています。
新政府高官は驚く程の高級と広大な邸宅を与えられ、大名暮らしの様な状態で特に財政経済担当の官僚は財閥と結び付き、贅沢を極めていました。
特に官業払下げを次々と実行した松方正義によって国富が財閥に流れ、財閥とそれと結託した政官財のグループ主義の力が支配を強めていきます。
それを行った松方正義は、財閥と姻戚関係を結び、子孫も繋がりによって多くの財界における重職に就いていきます。
陸奥宗光にしても、次男を古河財閥の二代目として養子にし、足尾銅山鉱山事件においては田中正造からの質問主意書に対して、質問の趣旨が分からないと、農商務相在任中に回答し、訴えを無視して、勝海舟に非難されています。
また自分の息子を古河財閥の社長にすると共に自分の側近である原敬を副社長にして、且つ従兄弟で代議士である岡崎邦輔を渉外係として監事にしています。
足尾銅山鉱毒事件で被害を受けた谷中村の強制土地収用公告を出した西園寺公望内閣の内務大臣は原敬であり、古河財閥の後ろ楯を受けながら、後に首相となります。
また、この事件時の鉱山保安局長は足尾銅山の鉱長に天下りしています。
こうした利益供与・天下り・閨閥が絡み合った政官財の三つ巴の癒着構造が民衆を犠牲にしていきます。
最後の元老といわれた西園寺公望に至っては、実弟が住友家に養子になり、住友財閥を継いでおり、西園寺の秘書であり、宮中グループの一員である原田熊雄は住友本社四階に部屋を持ち、報酬などは住友財閥から出ていました。
明治維新は、封建的な江戸時代に比較して、柵(しがらみ)や利権・癒着などが一度リセットされ、条件的客観的評価システムであるメリットシステムの整備などで、優れた人材が世に出やすくなりましたが、結果的客観的評価システムの欠如によって、時が経るにつれて、徐々に柵・利権・癒着の再構築がされて、改革を歪めていきます。
それは明治維新しかり、戦後民主主義しかりで、私党・縁故主義・グループ主義に走る人が報われるのではなく、公益に走る人が報われるシステムを創らないと改革をしても、すぐ後戻りしてしまいます。
戦後の日本はまさに縁故資本主義という状態でした。
人は成功すると、子孫を特権階級化したがる習性が集団欲により、本能として備わっていますが、それが暴走することによって、争いや戦争が発生していることが歴史的に分かります。
そのグループ主義的、縁故主義的なものを抑制するものが客観的評価システムであり、古代・中世と続いた封建時代を近現代の時代に脱しさせたのが、条件的客観的評価システムであるメリットシステムや民主主義から派性する結果的客観的評価システムでした。
戦前の日本では、前者は導入されましたが、後者は天皇主権の大日本帝国憲法の性質上、根付きませんでした。
後者が欠けた場合の中途半端な民主主義は古代ギリシャ、共和制ローマ、フランス革命後の共和政、ドイツのワイマール共和国の例を見ても、全て軍事的独裁に帰結しています。
きちんとした評価システムがなければ、国民はより良いものを選択する術や選択肢がなく、必然的に衆愚政治になるからです。
グループ主義や縁故主義が、歴史的に見ると争い・戦争・衆愚政治など、公益において、負の作用の大元的存在になっていることがよく分かります。
政官財癒着・元勲・天皇の取り巻き・それらの濃縮されたグループ主義・縁故主義の中心にあったのが、宮中グループといえます。
彼らは優秀であったから実権を握ったのではなく、血筋が良いというだけで日本の舵取りを任されます。西園寺公望・牧野伸顕から近衛文麿・木戸幸一と二代三代と代を重ねる毎に質が劣化するのは、縁故主義の象徴的存在である封建時代の王朝の全てに共通することと同様です。
優秀な人材をセレクトする選択肢が代を重ねる毎に、徐々に癒着・柵などによる縁故主義に狭められるため当然のことといえます。
『国民政府を対手とせず』という声明によって和平の道を閉ざし、日中戦争を長期化させ、国内では政党を全て解党させ、大政翼賛会を組織させた近衛文麿やカウンタークーデターを画策した陸軍の統制派と結託し、日中戦争に反対していた皇道派を粛清させ、天皇の側近である内大臣として、国運を左右する(内閣の首班を天皇に推薦するなど)影響力を持ちながら、東条英機を推挙するなど日本を敗戦の道へと迷い込ませた木戸幸一など宮中グループの面々が質的に劣化した道筋を残してしまうのは、決して彼らが先天的に、総合的な能力という点で劣っているという訳ではなく、二つの要因が考えられます。
一つは適材適所という観点での要因です。
北宋を滅亡に導いた徽宗皇帝は芸術家としては一流であったといわれ、文人・画人としての徽宗はその才能が高く評価され、芸術面では北宋最高の一人といわれています。
しかし、政治家として、皇帝としては全く無能であり、靖康の変など多くの国の民が苦しみに喘ぐことになりました。
北宋の神宗と徽宗、前漢の宣帝と元帝を見ても、二代続いて名君が続くのは稀で、封建時代の世襲制度や戦前の日本における近い縁戚同士での縁故主義的なセレクトよりも、幅広い・広範囲における・公平性のある・社会の利益に沿った客観的評価システムなどで、熱意のある志願者からセレクトする方が優れた人材が選出されることは当然のことといえます。
もう一つは改革精神・ハングリー精神という観点での要因です。
強い志がなければ、自然の流れで癒着・グループ主義・縁故主義の流れに沿っていくのは、本能における集団欲の作用の働きによって当然の理となります。
その流れに逆らってイノベーションを起こすのは、逆境や恵まれていない環境で育ち、既得権益の外からの視点を持つ人物でないと、余程、変革を迫られるような環境になるか、優秀なブレーンが幸運にもいるかしない限り、非常に困難になります。
実際に、名君といわれ、中興の祖といわれている前漢の宣帝、明の弘治帝、清の康熙帝、朝鮮王朝の正祖、江戸時代の徳川吉宗などは本来ならばトップに立てる環境にないか、庶民や、反主流派の中で育てられた者がほとんどです。
順当に、直系で皇太子という系統でトップに立った者は、トップに立つ前に、既に既得権益による取り巻きが形成されてしまい、既得権益外の視点での情報が遮断されてしまい、たとえ名君・ダイヤモンド的素質があったとしても、磨かれずに、原石のままに生涯を閉じてしまいます。
ローマ帝国の最盛期は五賢帝時代ですが、五賢帝の最後の皇帝マルクス・アウレリウスが直系である実子のコンモドゥスを後継者に選んだ時から帝国の斜陽の時代が始まっています。
人の痛みや苦しみを自らの経験などによって理解し、社会の本質をあらゆる角度で深く探求しながら、人的資源を切磋琢磨していかないと、ダイヤモンドの原石であっても石のままになってしまいます。
何もかも与えられ、優遇された環境下では、改革的な考え方は生まれにくいものです。
集団欲によって癒着の方向性に流れ、そこに辿り着くと、どんどん停滞していくのが自然の流れで、水が停滞すると腐るように、常に改善への方向性と流れをもたないと腐敗が蓄積されることになります。
大きく社会を変革した歴史的人物の多くは逆境や大きな困難を経験しています。
坂本龍馬にしても、土佐藩の厳しい身分差別の中で育ったからこそ、その矛盾を改革する強い志も育ったといえます。
北一輝にしても、裕福な家庭に育ち、学業においえも飛び級で進級しますが、家業の造り酒屋が傾いたことと眼病によって退学してからは、経済的・社会的にも苦学をしていきます。
もし、眼病を患わず、実家も傾かなければ、順当に進学して、メリットシステムの下で官僚となり、政官財のグループ主義に取り込まれて、改革の必要性と志を深く感じず、もしくは感じても、その濃度は薄まるか、グループ主義の柵(しがらみ)による制限により、大きな働きができなかった可能性があります。
アメリカが、世界一の超大国として、長期間において君臨しているのも、アメリカンドリームで象徴されるように、マイノリティ層がさまざまな分野で、イノベーションを起こし、牽引してきたことが大きな理由といわれています。
これらの二つの要因によって、既得権益と縁故主義の狭い範囲で選出された者が社会の舵取りをすることは、歴史的に見て、大きな不幸に直結することになっています。
これらの既得権益・縁故主義の狭い範囲からセレクトされた者からも、極少数ながら公益に沿った改革派指向の優秀な者達が生まれ、グループ主義に反する行動をすることがあります。
グラックス兄弟やケネディ兄弟です。
しかし、彼らは、彼らを押し上げたグループ主義に反する行動をとったため、暗殺されてしまいます。
最後に残ったケネディ兄弟の末弟のエドワード・ケネディは暗殺を恐れて、行動を控えてしまいます。
この様に、グループ主義に反して、迫害されるのであれば、特権階級内では真に改革をしようする者は後を続かなくなり、逆にグループ主義に沿った方が、実権を握れ、優遇されるのであれば、圧倒的多数はその方向性に流れることになります。
よって、改革の主軸となるのは、やはり精神的要素からいっても、特権階級外の者達に懸っていると言えますが、グラックス兄弟・ケネディ兄弟の様に特権階級出身で権限を与えられていても非常に困難な改革を成し遂げるには、不可能と思える状況下でも、強固な意志・熱情を失わずに試行錯誤を繰り返さなければなりません。
坂本龍馬しかり北一輝しかりです。
坂本龍馬は、アヘンを中国に密貿易で輸出してロビー活動でイギリス国会における軍の派遣を決定させてアヘン戦争を引き起こした植民地主義の権化ともいえるマセソン紹介の長崎代理人であるグラバーから、北一輝は財閥から資金を得ていました。
本来ならば思想的に敵対する所から利益を得ている形となります。
しかし、二人とも、取り込まれることなく行動します。
坂本龍馬は戊辰戦争を回避するために、北一輝は財閥などの金融独占資本が政界・軍部・官僚・重臣と結合し、大衆を如何に苦しめているか明らかにしようと行動します。
その為、二人ともに暗殺もしくは無実の罪で処刑されてしまいます。
植民地主義・独占資本主義・縁故資本主義のグループ主義に取り込まれたのは、明治維新を一流といわれた維新志士が礎となり創り上げた後に亡くなったり、主流から外されたりしてから、実権を握った二流三流の人々で、彼らがその後の舵取りをして行き、その主流の流れは宮中グループと化していきます。
伊藤博文や井上馨はマセソン商会の資金や手配でイギリス留学をし、後の戦後宮中グループの中心となる吉田茂の養父はマセソン商会の横浜支店長を務め、莫大な資産が吉田茂に残され、実父の竹内綱は高島炭坑の経営においてマセソン商会と提携し、莫大な利益を得ています。
植民地主義、戦争を引き起こして利益を得る死の商人としての代表格であるマセソン商会、独占資本化した財閥のグループ主義の人脈・縁故・繋がりは見えない所で網目状に強固に広がっていました。
2,26事件で処刑された安田優少尉も非公開の暗黒裁判と化した法廷で、『軍上層部が戦時統制経済によって独占利益を貪ろうとする財閥に懐柔され、思うがままに操られてしまうと、国家は意図的に引き起こされる戦争によって滅亡の危機に直面しかねない。』と国を憂う発言をしています。
実際、その後、宮中グループと軍上層部である統制派によって、日中戦争を拡大させ、戦時統制経済の中、財閥は莫大に肥大化した軍事費から流れる軍需産業を寡占していることなどから莫大な利益を得ています。
はるかに、統制派以上に財閥と密接に結合していた宮中グループは敗戦が濃厚になると、保身の為に、統制派に全ての責任を押し付けようとします。
近衛文麿の言にも『せっかく東条がヒットラーと共に世界の憎まれ役になっているのだから、彼に全責任を負わしめるのが良いと思う』や東久邇宮稔彦王も『悪くなったら皆東条が悪いのだ。全ての責任を東条にしょっかぶせるがよいと思うのだ』という言を残しています。
統制派に全ての責任を押し付けた、真の戦争責任者である宮中グループの一部は温存されます。
戦後宮中グループの中心となる吉田茂は中国における日本の権益に関しては軍部よりも強硬であったことは有名です。
また、吉田の側近として戦後において政治的に大きな影響力を持った白洲次郎は、日本最大・最新鋭の製鉄所をイギリス企業から莫大な手数料を自らが得るために、イギリス企業に売却を主唱したり、日本独自の日本航空の成立に対抗して、アメリカの航空会社の資本による設立を画策しています。
彼らは決して、非帝国主義的、戦後民主主義的な思想を持っていたわけではなく、帝国主義的に英米に追従しながら利権を得ようとするものだったと思われます。
温存されたグループは戦前と同じ様に、閨閥グループを何重にも形成し、政官財癒着の縁故資本主義を再び構築していき、戦後民主改革の莫大な公益を時間をかけて削合していきます。
ドイツでは敗戦によって、国家体制もナチス党も崩壊し、旧ナチス党であった者は、徹底的に追及されるとともに、官僚制も、それまでの七十五%もの官僚」が解雇され、政権を支え、協力してきた土台が替えられました。
一方、日本では、官僚組織はそのまま残され、戦前戦後一貫して強力なグループ主義・縁故主義は度合の差はあれど実権を握り続けていきます。
その度合は勿論、戦前の方がはるかに強く、言論統制がされ、特高警察、治安維持法、暗黒裁判など武力に裏打ちされた圧政の分、戦後よりもそのグループ主義は強力でした。
しかし、戦後民主改革によって、それらが大きく解除された状態でも、官僚を中心としたグループ主義、縁故主義は改革を試みる動きを悉く無効にして、実権を握って来た経過を見ると、さらに強固であった戦前のグループ主義と対峙することは非常に困難で、不可能に近いことに思われます。
北一輝はこの不可能とも思える困難な課題に対して、初めは非武力的アプローチをして行きますが、悉く著作物が発禁処分を受けてしまいます。
その後、中国における民主革命といえる辛亥革命を渡航して直接支援を命懸けでした経験から、武力による圧政を解除するには、武力的要素が必要であることを認識し始めます。民主革命のほとんどは武力が介在し、戦後民主改革も、アメリカの武力を背景になされたことからも、この認識の必要性は歴史的にも裏打ちされています。(詳しくはこちら)
北は革命を遂行する主体は、『支那革命外史』『日本改造法案大綱』に述べられている様に、軍隊の上層部は必ず時の政治権力に密着し、腐敗しているため、下級士官が下士官・兵卒を握って、それにならなければならないと主張し、青年将校と交流していきます。明治政府の主流となった長州閥の思想的祖であり、精神的支柱であった吉田松陰は事あるごとに暗殺を主張し、強い対外侵略思想を持っていたことと対比すると、北は直接に暗殺などに関与したことはなく、間接的に思想的に影響を与えたり、資金を得るために(詳しくはこちら)事件を利用することはあっても極めて緩やかなものだったと言えます。
また、北が悉く5, 15事件や2,26事件など決起に反対してきたことは、先ず国際間の調整が緊急であるという考えがあったにせよ、主たる理由としてはそれらの決起によって真崎内閣や柳川内閣のような軍上層部が主体となった政権が成立しても国家社会主義的色彩濃厚なものであって、北の改造法案とは全く異なっており、北自身余り期待していなかったためでした。
そのことは、2,26事件の聴取書に北の述べた言葉の中に綴られています。
ただ、事件の収拾策として真崎大将に一任を勧めたのは、真崎大将に一任させれば青年将校をむざむざ犠牲にすることはあるまいと考えたからでした。
しかし、真崎大将は青年将校を切り捨て、保身に走ります。北が青年将校のために殉じたのはその様な行き場のなくなった彼らの想いを救うためでもありました。
また、北は天皇帰一の矛盾を表面化させるために、敢えて自らの考え方と対極にある統帥権干犯の問題に着目し、知恵を軍や野党につけさせ、追及させます。
これによって、軍部が統帥権を盾に取り台頭したといわれていますが、これは王安石に朋党の争いの原因を無理矢理に押し付けたことと同様で、軍部が台頭した主たる原因は全く別にありました。
大正時代は、大正デモクラシーの下で民主的風潮が広まり、また第一次世界大戦後の軍縮の流れもあって、軍人軽視・軍部蔑視の風潮が生み出されていました。
それが一変し、軍部が力をつけて台頭していくのは、憲政の常道期を経てからです。
つまり、憲政の常道期における中途半端な民主主義によって、民主主義の長所の恩恵は受けられず、欠点である金権政治・腐敗のみがクローズドアップされ、国民の信頼が政党政治や民主主義から距離ができてしまったことから、軍部の台頭が始まります。
これは、歴史的に見ても、古代ローマ、フランス革命しばらくの間のフランス、ワイマール共和国時代のドイツなど中途半端な民主主義から民主主義の欠点である金権政治・腐敗・衆愚政治によって、軍部の台頭、独裁に帰結していることから見ても明らかです。天皇主権を隠れ蓑に、中途半端な民主主義を創り上げた宮中グループ・官僚・財閥などのグループ主義こそが主原因であり、北一輝はその矛盾を明らかにし、それらを改革しようと試みただけだったことが残された言動などからも分かります。
統帥権干犯問題に関与したことによってファシストとなるのであれば、議会においてそのことを口実に、実際に政府を攻撃した当時野党の政友会の犬養毅や鳩山一郎はまさにその対象になってしまいます。
また、同じ明治憲法体制を少し遡ると、福沢諭吉や植木枝盛も盛んに統帥権の独立を叫んでいます。
彼らも、ファシスト的なものを意図して、それらの行動をした訳ではなく、他の意図があっての行動であったと思われます。
それを無視して、一つの視点だけの観点で集中して拡大解釈してしまうと、どのような人物でもとてつもなく大きな非難の対象となってしまいます。
これらは、まさに北宋における王安石の朋党の争いと同じケースといえます。
次に資本の国家による干渉・規制の問題に移ります。
対外政策における統制派や宮中グループが組み立てたファシズム的なものと北の改造法案の内容が質的には全く異なるものであった様に、これらに関しても全く同じことが当て嵌まります。
国家が企業の経済活動に一切関与しない純粋な資本主義が成立することが困難であることを世界恐慌を経て、各国が認識し始める時代でした。
そのまま自由にしてしまうと、利益を追求する余り、過剰な生産などから深刻な恐慌が起こってしまうからです。
資本主義のシステムは、客観的評価システムの観点から見ると、評価するするための極めて有効なアイテムでは在りますが、それ自体は客観的評価システムの一種ではなく、たとえその様に規定したとしても、極めて初歩的なものといえます。
貨幣経済やそれは発展した資本主義のシステムがなければ、客観的評価システムの評価・報酬が土地や身分・特権階級など硬直的なものに限定されてしまいます。
また、資本的利益を上げることが社会の利益にイコールかと言えば、そうではなく、資本の利益のみを追及したが為に、独占資本などによる帝国主義的な侵略・戦争、過剰生産などによる深刻な恐慌、現代においては最も懸念されている環境破壊などの大きな問題が続出しています。
資本主義のシステムは他の客観的評価システムを十分に機能させるために必要不可欠なものではありますが、それ自体に十分な客観的評価システム機能がないため、資本主義経済を管理するための他の客観的評価システムの存在も必要不可欠となります。
各国はその管理を政府・国家が積極的に行うようにしていきます。
つまり、国家による資本の干渉・規制が機能する混合経済・修正資本主義というものです。
しかし、その管理を行う政府に客観的評価システムが波及していなければ、当然に資本主義経済にも波及しない形となります。
民主主義から派生し、そしてその民主主義を安定に導く結果的客観的評価システムはソ連やナチス、戦前日本のような独裁国家下では原則的には機能しません。
また、たとえ安定した民主国とされていても、客観的評価システムの機能が不十分な国では、官僚の暴走、無駄使いを起因とした財政赤字の問題が大きく浮上して来ます。
この際、政府の大きい・小さいの問題よりも、客観的評価システムの機能が十分かどうかが重要となります。
機能が優れていると、逆に大きな政府の方が財政赤字が少なくなります。スゥエーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランドなど北欧諸国は公務員数が多く大きな政府であっても財政赤字は少なくなっています。
北欧諸国に比較すると公務員数の比率が少ないながら、戦後民主改革によって獲得された結果的客観的評価システムを、温存されたグループ主義によってその機能が落とされていった日本が先進国随一の財政赤字国になっていることを見ても分かります。
北一輝の改造法案における経済構造変革に関する基本構想は、国有化至上のソ連型社会主義ではなく、私企業至上主義の資本主義でもない、独自の混合経済体制の構築でした。
大資本を要し、強力な対外競争力を必要とする分野は大資本の国家的統一を行うと同時に、私企業の必要性を認め、私有財産制に基づく自由主義的な機材制度を基本とし、小資本による私人経済が予見できる将来において経済活動の大部分を占めるだろうという現実的判断の下、従来民間の参入を排除していた産業分野を民営化するというものです。
つまり、具体的に言うと、国鉄の独占ではなく、支線鉄道の民営解放、塩と煙草の専売制度廃止などです。
しかし、積極的な私企業・民営肯定論だけでは経済活動における財閥の比重が増大するにつれて、独占資本と大地主の連合が政党を支配し、官僚を取り込み、軍部を動かし、帝国主義的な侵略を行っている状況を打破することはできません。
北は財閥の権力を制限する為に、法案では、私的企業の資本金上限額を一千万円としますが、現代で換算すると三百億円となり、当時資本金一千万円の企業と言えば鴻池銀行、伊藤商事などのかなりの大会社であり、大規模な私企業の活動が認められている形となっていました。
そして何より、『国民主権』、『言論の自由』、『基本的人権の尊重』、『治安維持法の廃止』、『普通選挙』、『貴族院・枢密院の廃止』などによって、安定した民主主義の道筋が根付けられているため、政府に対する民主的コントロールつまり、結果的客観的評価システムが機能する方向性となります。
北の改造法案の内容は、作家の三島由紀夫(皇国主義者である三島自身は戦後民主主義や北の思想には批判的でしたが)が述べている様に、日本国憲法、戦後民主改革によってほぼ実現されたと言えます。
上記内容(『』の中)や、国民の天皇、華族制の禁止、国民自由の回復を声高に歌い、国民の自由を拘束する新聞紙条例や出版法の廃止を主張していますが、これらは全て、日本国憲法によって実現されたもので、私有財産の限度も、日本国民一人の所有するべき財産の限度を3百万円、現代の百億円と規定されていますが、実質的には戦後の累進課税・相続税その他の負担が自ずから改造法案の目的をほぼ実現してしまっています。
また、大資本の国家統一についても、戦後の護送船団方式によって同様のことが言えます。
逆に言えば、北の改造法案が日本の戦後民主時代を創り上げたと言えます。
改造法案が日本国憲法の雛形となり、その思想に影響を受けた人々が国内外問わず、戦後日本の政治の舵取りに深く関与したことを考慮すると判ります。
しかし、戦前の実権を握っていたグループ主義の根本部分が温存されたためために、戦後民主改革によって一度は大きく解除されたグループ主義が、少しずつ再構築されていきことにより、戦後民主制度が歪められ、グループ主義の暴走が再び進行していきます。
彼らが完全に実権を握っていた戦前の憲政の常道期においての民主主義といわれたものの実態は、首相を選出する権限は宮中にあり、歴代総理大臣は二人を除けば、衆議院議員でなく、国民代表とはとても言えない貴族院議員であり、政党内閣の最高指導者の半数以上は、自らに対する選挙の洗礼を恐れなくていい人々でありました。
また政友会は三井財閥、民政党は三菱財閥など政党と財閥の結託や腐敗が著しく、また選挙の度に政権党がかつという不可思議な現象が常態化しました。
つまり、本来は政党間の政権交代は総選挙という国民の審判を通じて行われるべきであるのが、野党の政党は官僚・枢密院・財閥・軍部などの勢力と結んで倒閣を目指し、それを果たした野党の政党が議会の少数派のままで組閣し、与党という有利な条件の下で総選挙に勝って第一党に躍進するという形式が政権交代の基本的形式となっていました。
政権交代の度に百人単位で官僚が入れ替わり、政権党系の府県知事や警察幹部などが配置され、選挙干渉を行うというものです。
この為、国内外問題が山積みの状態なのに政党においては党利党略が最優先され、抗争だけが進行し、問題解決はほとんどされない状況で、国民の民主政治への不信感の延長線からの軍部台頭における統制経済下などでは、安定した民主政治から派生する結果的客観的評価システムの裏打ちは望めるはずがありません。
それに対して、北の目指した政府における経済・資本における規制などは、結果的客観的評価システムの機能の裏打ちを伴うものである点で全く質的に異なるものと言えます。
この様に、北の方向性は、戦後民主義の雛形である以上、当然その方向性とほぼ同方向であるのを無理やり、戦前のファシストと類似点をピックアップし、そのレッテルが貼られてしまいます。
その類似点も質的に別物であり、この戦前は民主主義者として非難し、戦後はファシストとして非難する矛盾極まりない論理が常道として通ってしまうということは、王安石の例を見ても、日本の戦前から続くグループ主義は戦後改革によって弱められ、メンバーがいくらか変わったにしても根強く、実権を保持していることが分かります。
北の再評価がされるのも、王安石の再評価と同様、体制の大きな変化と共に実行されるであろうことが予測できます。
つまり、官僚、縁故主義のグループ主義が結果的客観的評価システムによって、しっかり制御されるシステムが根付く時であると思われます。
歴史における通説というのは総じて、勝者の論理、当時の社会的強者、体制サイドの主観的なフィルターによって歪められてしまう傾向にあるのが残念ながら世の常といえます。
よって今回は判官びいきが過ぎるといわれるかもしれませんが、一般に国賊といわれたサイドの観点で考察をアプローチしています。
天皇制は日本人のアイデンティティの象徴であり、皆で守り存続させるべき貴重で大切な制度です。
また、天皇陛下は日本国民の良心的精神の支柱です。(上記や他記事では制度的表現で記述しているため陛下の尊称は省略させていただいております。)
だからこそ、それが悪用され、戦前の様に全ての国民が地獄の苦しみに喘ぐようなことが二度とあってはなりません。
そのためには、戦後からどれだけ年数が経ったとしても、やはり過去をしっかりと直視し、その総括をしなければなりません。
かといって宮中グループの人々をめいめい個人攻撃するつもりは全くありません。
その行為は本ブログの主旨である人物や組織を極力非難することなく 、否定することなく、どうすれば全ての人が幸せになる 社会のシステムを 構築できるかを歴史的観点から模索し追求していくという方向性に反することにもなります。
その様な環境下に生まれ、権限を付与されれば、ほとんどの人(自分も含めて)がほぼ同様の行動をとってしまうと思います。
大事なことはそうならないシステムを皆で構築していかなければならないという必要性を皆全員が認識していくことにあると思います。