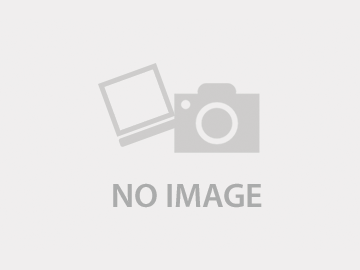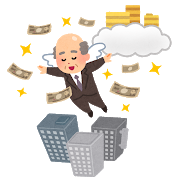その後、古代・中世の時代においては、ローマ帝国ほどの繁栄を示す国は現れませんでした。
経済規模の指標となる銀の産出量の比較にしても、古代ローマが最も繁栄した五賢帝時代の1世紀に最大になり、その後減少していき、1世紀と同じ数字に戻るのは近代の18世紀半ばになってからになります。
記事の目次
①ローマ崩壊後の暗黒時代
ローマ崩壊後、西欧地方は貨幣経済が衰退し、自給自足の中で貴族制・封建制の血縁を中心としたクループ主義、武力による領土争い、固定的な階級社会となり、いわゆる暗黒時代という戦争の時代が続きます。
貨幣経済や交易が衰えた中では、自らの資源だけで生きていかなければならず、絶えず略奪的襲撃が行われる時代でもありました。
また宗教的に寛容であったローマ帝国時代と異なり、この時代はキリスト教のカトリック教会が皇帝や国王を上回る権力を握り、人間形成や学問研究に対しても大きな支配権を所有していました。
カトリックは素晴らしい宗教です。
最も尊敬すべき歴史的人物ともいえるケネディ大統領もカトリック教徒であり、現代のローマ教皇が世界的な平和・公益に大きく貢献されていることはだれもが認めるところです。
しかし、どんな宗教・思想も長所もあれば短所もあります。背景となる時代・環境・状況下によっては大きく+(プラス)に作用したり、-(マイナス)に作用したりします。
聖書は一般の信者の人々には与えられず、またラテン語で読まれたため、一般の人々には理解されませんでした。
よって信者は聖書に救いや信仰の拠り所を求めるのではなく、教会に求める形となります。
カトリック教会は教皇を頂点とした階層制組織を築き上げていたために、教皇を中心とした一部の聖職者上層部グループの裁量・主観的判断によって、一方的に教義を決定し、信者も教会やローマ教皇の言うことはすべて正しいと疑うことなく信じ切っていました。
ローマ教皇が最高権力者、信仰については全ての誤りから免れ、守られている者、彼への忠誠は救済の絶対条件でカトリック教会の聖職者のみが祭司の権威を持ち、神の恵みを与えて、罪を赦す権威を授けられているという理解は、聖書に反するものであり、またカトリックの儀式や教えの中にある現象の多くが、聖書の中に書かれてなかったり、禁じられている事柄も含まれていたりしました。
特定のグループの裁量・主観的判断に大きな権限を与えた時は、前述したとおり、歴史的にみるとほとんどのケースで癒着・腐敗が進行してしまっています。
実際に、時代が経るにつれ、教会の世俗化や腐敗・堕落は進行をしました。
カトリック教会は、信者に対しては蓄財や富に否定的な考え方を示し、清貧を強いて、貯蓄よりも寄付を誘導しため、貨幣経済が浸透しにくい状態が続きました。
原始時代や山奥の点在した集落などの集団同士の接触がほとんどない状態でなければ、貨幣経済が発展しない自給自足の社会においては、天候不順などで食料や資源が欠乏した時、略奪的行為や紛争が頻発する傾向があります。
交易・流通が発達せず、各自が欠乏したものと交換可能な価値の通貨などの蓄えがないと飢饉にもなりやすく、さらに略奪や紛争が起こりやすくなってしまいます。
貨幣経済が衰退していたために富の基本が土地であった時代において、教会が所有する土地は西ヨーロッパの20%から30%までなり、教会は極めて裕福で巨大な組織となりました。
救いを得るために、有力者や諸侯は教会に寄進しただけに留まらず、次男や三男を聖職者とし、寄進が大きいほど高い地位に就けたために、競って寄進が行われ、既得権益との融合・腐敗は進展していきました。
この時代はカトリック教会の絶対主義の中、停滞と紛争の暗黒時代と呼ばれています。
②東欧での繁栄
ローマ帝国分裂後、東欧では西欧で西ローマ帝国がすぐ崩壊したのとは違い、東ローマ帝国は全盛期のローマ帝国と形は変われど、中世15世紀半ばまで存続します。
西欧でのカトリック教会と異なり、東欧ではギリシア正教会が宗教における中心的役割を担っていきます。
東欧では都市部の市民の識字率が比較的高く、ギリシア人の一般民衆でも聖書を読むことができ、聖書もギリシア語で書かれたものが流布していました。
教義を最終的に決定するのは、皇帝でも総主教でもなく、教会会議によるものとされていたため、活発な議論が展開されることになります。
教会側が主観的に一方的に教義を決定することができたカトリック教会に比較して、客観的要素がギリシア正教会の方があったと思われます。東欧では西欧と異なり、古代以来の貨幣経済制度が機能し続け、帝国発行のノミスマ金貨は11世紀前半まで高い純度を保ち、後世において『中世のドル』と 呼ばれるほどの国際的貨幣として流通しました。
東方との貿易などが帝国に多くの富をもたらし、首都のコンスタンティノポリスは世界の富の2/3が集まる所と言われるほど繁栄しました。
③十字軍とルネッサンス、そして宗教改革へ
西側世界においては、慢性的な食糧危機に喘ぎ、大飢饉、疾病などにより、荒廃を極め、領主たちは自分たちの領土を少しでも増やそうと戦いに明け暮れていて、早急に新しい土地と富が必要な状態でした。
その中で、東ローマ帝国からの少数の傭兵の援軍要請が届きます。
カトリックの教皇のウルバヌス二世は、慢性的な食料、領土不足を解消するために、主観的要素を加えて大げさに吹聴し、民衆を煽り立て、危機感を募らせて、聖戦ムードを演出し、数万を数える大規模な遠征部隊を送ります。
そして、その後長期間に渡り、十字軍として何度も遠征部隊が派遣されることになります。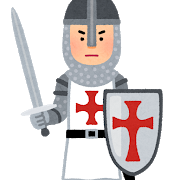
ウルバヌス二世の名演説といわれる主観的・好戦的で外部に絶対的な敵を作り、暴力的な対応を提唱した弁論術に長けた主張は民衆の感情に火をつけ、それは人々の信仰心と集団と集団ヒステリーが結合した形で、聖戦などとは程遠い凄惨な怪物的ともいえる十字軍の残虐行為を生み出しました。
第4回十字軍の時は味方側であるはずの東ローマ帝国の首都であるコンスタンチノープルを攻撃し、陥落させ、略奪・殺戮の限りを尽くし、東ローマ帝国を一旦滅亡させます。
その後、東ローマ帝国は復興しますが、多大な人力・財力が奪われ、弱体化したために実質的、この時期13世紀に滅亡したと見る歴史家もいます。
十字軍によって東欧は大きな被害を受けますが、西欧では十字軍を契機にビザンツやイスラム文明が流入し、古典文化の復興を謳ったルネッサンスが花開きます。
それまでの西欧ではローマ教会中心主義が人々に浸透し、ギリシア・ローマ時代の科学、哲学、技術の知識を否定してしまい、かってローマ帝国が築いた水道橋や大規模な公共建築物を巨人の造ったもの、魔法使いが作り上げたなどと呼び、その技術知識を継承できなかった状態でした。
地元であるローマを含む西欧よりもローマ文明の英知を継承できた東欧やイスラム圏の方が経済的・文化的にも格段に良い生活様式を持っていました。
それらの文明が西欧に流入したことによって、古代文化の復興の動きが起こり、その一環として聖書のギリシア語原文の研究とそれに伴う聖書解釈の再検討が始まります。
この聖書解釈の再検討はすなわち、当時のカトリック教会の絶対主義を揺るがす事になり、宗教改革へと繋がっていきます。
長きに渡る停滞の暗黒時代を抜けることとカトリック教会の権力が衰えることは強い相関関係をもって、同時に並行して進行していきます。
宗教改革は14世紀、ウィクリフによって始まります。ウィクリフはカトリックの教義は聖書から離れていると批判します。
本来の教会は一般に教会が主張する階層制度ではなく、その長は教皇ではなく、キリストであり、教皇に従えば救済を受けられるなど条文には書いていないというものです。
聖書のみを信仰の基準として、宗教改革・プロテスタント運動は進んでいきます。
ルターにより免罪符・教会の聖職位階制度・聖書に根拠のない秘跡や慣習が非難され、聖書が訳されて出版されるに至ってはヨーロッパ中に波及していきます。
④救済の基準に対しての主観的裁量から客観的な基準への移行と資本主義経済の発達
カトリックが聖書を信者が読めないことから、教義を階層制度の下で教皇を中心とした上層部が主観的に決定したのに対して、プロテスタントは聖書に書かれていることのみを根拠とする客観的なものでした。
またプロテスタントでは、神の下で人々の平等を主張し、カトリックの身分制を否定し、信徒は皆平等で、教会聖職者を信徒の上位に置くことを認めませんでした。さらにプロテスタントの一派であるカルヴァン派では、予定説という人に神が救済を与えるかどうかは予め決定されており、この世で善行を積んだかどうかといったことではそれを変えることはできないという聖書の教理の解釈を前面に出していきます。
つまり教会にいくら寄進をしても救済されるかどうかには全く関係ないというものです。
大体の宗教では、救済、救いというものを前面に押し出して来ます。
既得権益化した上層部が主観的判断つまり裁量で、それらの基準を操作することが莫大な権益となっていまいました。
日本でも戦国時代において、日本の八大金持ちとされたものに、寺社は四つも含まれています。
石山本願寺においては、イエズス会の者により『日本の富の大部分はこの坊主の所有である』と書かれるほど財力を有し、戦国大名と姻戚を結ぶなどカトリック教会と同じように、封建制度の既得権層との密接な繋がりを持っていました。
プロテスタントがこの救いの裁量を捨てたことは、宗教の歴史の中では極めて特殊であると言えます。
また世俗の労働を励むことによって、社会に貢献し、その結果としての収益・業績が救いの証とされたことから、プロテスタント、特にカルヴァン派の中から資本主義経済の発達が生まれ、そして民主主義思想も再び復活して来ます。
プロテスタント共通の万人祭司、つまり特権的聖職者の存在を否定する考え方、神の下に平等という考え方、そしてカルヴァン派においては、救済の基準に対し、主観的裁量からという客観的な基準(救いの証としての収益)に変化したことなどから、今までのカトリックはもちろん他の宗教が既存の封建階層と密接に繋がり、場合によってはほぼ一体化し、その存続を強固に補強してきた貴族制・封建制を崩壊させ、資本主義・民主主義が推し進められていきます。
プロテスタント、その中でもカルヴァン派が多数派を占めるようになった小国オランダは、独立戦争でカトリック国である大国スペインに勝利し、17世紀において世界的な経済超大国・世界最大の貿易国家となります。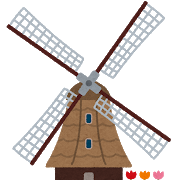
オランダの絶頂期である17世紀半ばにおいて、オランダの海上覇権・商業覇権は揺るぎないものになります。全世界の貿易船の総数が2万あったのに対して、オランダ船は1万5000以上あり、フランスがオランダの20倍の人口がある中で、オランダ海軍はフランス海軍とイギリス海軍の合計に匹敵する規模でした。
オランダを弱小国から最大の覇権国にまで成長させたのは、全欧州からプロテスタントの商人・熟練工・産業家たちが大量に流入して、砂糖精製から武器製造や化学工業に至るまでのありとあらゆる産業において、ヨーロッパ随一の地位まで登り詰めたからで、新教徒、プロテスタントの多くは洗練された特技を持った熟練職人であったり、有力な資本家でありました。
オランダの人口の2割から3割はカトリックでしたが、世界初の株式会社と言われる東インド会社の出資者は一人残らずプロテスタントでした。
オランダでは道徳的にも政治的にも当時の諸外国と比べると自由主義が住んでいました。
オランダを訪れた外国人は召使いが主人に対して、妻が夫に対して、また庶民が貴族に対して示す尊敬の度合いが余りにも低いことに衝撃を受けています。
オランダのメイドは服装といい、振る舞いといい、女主人に似通い過ぎており、見分けがつかないというものです。
オランダの人々は、老若男女、身分を問わず、皆独立自尊であり、好きな仕事をし、商売をし、誰が金持ちになるにも制限がないとオランダよりもずっと硬直的な社会秩序に慣れた同時代の他のヨーロッパ人からはそう見られていました。
これは、プロテスタントの神の下に平等の考え方とカルヴァン派の教義によって急速に発達した資本主義の影響が大きく関与しています。
報酬制度として、封建制のような固定的な土地や特権階級を主とする場合は、貴族性などの血縁を中心とする身分制やグループ主義の影響を受けやすいですが、流動的である貨幣などを主とする場合では、身分的にも当然に流動化しやすく、貴族階級のような存在が成立しにくくなります。
それらの200年後のアメリカンドリームのような努力をすれば報われるという現象が起き、寛容と高賃金などの吸引力などによって熟練工や才能豊かな人材が全ヨーロッパからオランダに集まり、大学にも様々な外国人が集まり、人口の過半数が移民か移民の子孫となっていました。
まさにそれは、その後の覇権国となるアメリカと酷似した現象となりますが、アメリカもカルヴァン派のピューリタンなどのプロテスタントの移民が中心に建国されていくことを考えると当然のことと言えます。
その後17世紀末期に、オランダ海軍の大艦隊がイギリスに侵攻し、オランダ兵がロンドンを占領し、オランダ執政オラニエ公ウィレム3世がイギリス王として即位、妻のメアリーと共同でイギリスを統治することになりました。
オランダの優位が絶頂に達し、オランダの商業面・軍事面での拡大は誰にも止められないかに見られましたが、ウィレムがイギリス王になったことをきっかけに世界覇権国の座はオランダからイギリスに移っていきます。
その当時のイギリスがどのような状態であったかは、少し遡って、16世紀頃から見ていきます。
イギリスにおける教会領は王国の1/3を占めており、さらに加えて信徒から教会は貪欲に富を巻き上げて、その富はローマ教皇庁にそっくり送られていました。
しかし、イギリス国王であるヘンリー八世が離婚問題を機にカトリック教会と決別し、独自のイギリス国教会を成立させると、膨大な修道院領が没収され、富裕な市民階層に売却されていきます。
これらの富裕な市民階層が準貴族のジェントリーとしてこの払い下げにより台頭してきます。
封建主義的、固定的な既存の王侯・貴族・聖職者などの支配身分階層に比較して、ジェントリーは富を蓄積した市民や独立自営農民のヨーマンが土地を購入してジェントリーになったり、逆にジェントリーが没落するなどジェントリーの構成 メンバーは絶え間無く、入れ替わりました。
つまり、ジェントリーは極めて流動的な階層であって、この流動性がイギリスの階級対立を緩和する役割を果たし、さらに社会的・経済的に上昇を求める人々に活力を与えていきます。
エリザベス一世によって、イギリス国教会の教会制度は整えられていき、プロテスタントでありながら階層的に教会を監督・統制する主教制というカトリックの司教制度に近いものが採用される一方で、信仰義認説・聖書主義・予定説など教義はカルヴァン主義に近く、儀式はカトリック的なものを残すなど、プロテスタントとカトリックの中間的存在として存立していきます。
エリザベス一世の時代はイギリス・ルネッサンスの最盛期となり、対外的にもカトリック国のスペインの無敵艦隊を破って海外進出の端緒を開きました。
16世紀の宗教改革後、エリザベス1世の時代を経て、17世紀半ばまではジェントリーの台頭期と言われていますが、その土地保有が全体の25%から50%に増大しました。
君主から報酬として特定地域の支配権を付与される代わりに防衛や戦力提供の義務を負う軍務制度として設置される封建的貴族制度と違い、貨幣制度の中で商業などによる利益によって、土地保有が進められていき、伝統的封建貴族より商才に富んだ新興ジェントリーが台頭して行きます。
ジェントリーたちの新しい試みの中で最も成功したのは海外進出でしたが、初期にはカルヴァン派を国教とするオランダに圧倒され、イギリスは苦戦を強いられます。
オランダでも土地の貴族制は比較的重要ではなく、社会的なステータスは主に収入によって決められており、オランダ社会を支配していたのは都市の商人階級であり、階層間の分離は決定的なものではなく、カルヴァン派の思想が社会的差異の重要性を減少させ、社会的な流動性はイギリスよりも大きくありました。
当時のイギリスは大陸ヨーロッパのほとんどの国と何ら変わることなく、国内ではグループ主義の下、ひっきりなしに宗教戦争や人種間戦争が起こっており、イギリス国教会は反対派に弾圧を加え、そしてイギリス(イングランド)人はアイルランド人やスコットランド人、ウェールズ人を屠っていました。
それに比べてオランダでは宗教的寛容政策が進み、グループ主義的対立はイギリスに比べて少なかったことなどから、オランダのイギリスにおける優位性がありました 。
しかし、そのような状況の中でピューリタン革命は独裁に転じてしまい、その後王政復古によりカトリックの王建が復活すると、国教会派の議会の要請でオランダからイギリス国王の娘であるメアリーとその夫のオランダ総督のウィレムがオランダ軍を率いてイギリスに上陸し、無血クーデターで国王の交代が実現しました。
この革命、名誉革命以後イギリスはウィレムの下でオランダのシステムを取り入れていきます。
宗教のグループ主義を中心とするな内戦の永い時代を終わらせ、オランダと同じように宗教的・人種的寛容を取り入れていきます。
その中で、マイノリティ集団であったユグノーやスコットランド人などによって、イギリスは台頭して来ます。
ユグノーはフランスのプロテスタントのカルヴァン派の人々で、イギリスに亡命してきた人々です。
プロテスタントの多くは熟練工や有力な資本家が多いのは先述しましたが、オランダと同様にイギリスでも彼らは大きな利益を生み出します。
ユグノーの時計職人達によって、ロンドンは世界の時計製造業の中心へと成長し、その他製紙・金属細工など様々な技術がユグノーによってイギリスに持ち込まれます。
金融面においても、フランスとの戦争や内戦などによってできたイギリスの巨額債務の2割をも引き受けるなど大きな貢献をします。
国家権力上部からなされてカトリック的要素を残したイギリス(イングランド)の宗教改革と異なり、スコットランドの宗教改革は、下部から行われ、カルヴァン派のプロテスタントが国教とされました。
現在でもイングランドの各地には中世紀にカトリック教会として栄えたゴシック建築の会堂が今もなお聳え、イギリス国教会として利用されているのに比べ、スコットランドでは、カトリック教会の会堂はほとんど残っておらず、大聖堂も大寺院もことごとく破壊されているのは対照的でもあります。
スコットランド人は後の産業革命の原動力にもなり、産業革命において最も重要な発明と言える蒸気機関の開発者はスコットランド人のジェームズワットであり、さまざまな分野に人材を供給し、イギリス帝国はスコットランド帝国と呼んだ方が正確だという言葉さえ出ました。
また、イギリス国教会の中でも、カルヴァン派のピューリタンなど非国教徒との協力関係を保ち、名誉革命時にオランダの影響で定められた寛容法の精神に忠実に名誉革命体制の主体となったのがローチャーチと言われるプロテスタントの要素の強い人々でした。
先に繁栄したオランダにおいても、ユトレヒトやゴーダといったカトリックの影響が著しい都市では、黄金時代の繁栄を享受することは余りありませんでした。
オランダによって、イギリスはプロテスタントの要素が強くなるとともに、寛容の精神からグループ主義による対立・争いを減少させることにより、オランダに次ぐ覇権国として台頭していきます。
⑤民主主義から派生した結果的客観的評価システム
しかし、イギリスを揺るぎない世界の覇権国と足らしめたのは、民主主義から派生した政権党の政治に対して多数の国民による選挙における支持率という評価と政権を任せるという報酬による結果的客観的評価システムでした。
ウィリアム3世として即位したウィレムは子がなかったために、落馬事故で亡くなった後、メアリの妹のアンが王位を継承し、アン女王として即位しました。
アン女王も嫡子がないまま死去すると、遠縁にあたるドイツのハノーヴァー選帝侯が迎えられて、ジョージ1世として即位します。
しかし、この時、既に54歳で英語を解せず、イギリスの制度・慣習などについても知識がなかったために、イギリスよりもドイツに滞在することのほうが多く、政務を大臣たちに委ね、国王は君臨すれども統治せずという原則が確立しました。
1721年から20年間政権を担当したをウォルポール内閣から、内閣が議会に対し責任を持って国政を担当するという責任内閣制が成立し、議会政治は政党が選挙によって多数党の位置を競い、多数党が内閣を組織するという政党政治の枠組みが出来上がりました。
これによって、対立の暴力による決済に替わる体制内二党制が開始されました。
社会において改革しなければいけない事象が生まれた時、それを行うには必ず対立が伴います。
今までの長きに渡る歴史において、対立の暴力による決済がなされてきましたが、それは劇薬であり、副作用が強く、場合によっては、飲む前よりも対立が激化し、社会が荒廃してしまう危険性がありました。
かといって、それを恐れて改善が行われなければ、清流は常に流れなければ腐ってしまうように、社会も沈滞・衰退してしまいます。
それが、内戦・クデーターのような暴力を使わずに、平和裏に体制を大きく変革できるということは極めて画期的なことでした。
先の覇権国オランダにしても、人種的・宗教的なグループ主義的な対立は少なく、それが繁栄の礎にもなりましたが、対立は無になることは社会上決して有り得ません。
実際には大商人・都市貴族、宗教的には穏健的カルヴァン派が支持する連邦議会派と中小市民・農民層、宗教的には急進的カルヴァン派が支持する代々総督職を世襲して実質的なオランダ王家であったオラニエ家の対立がありました。
後には、それら都市貴族、オラニエ家などの従来の支配者層に代わってより徹底した共和制を求める愛国派も加わって、内戦状態になることも珍しくありませんでした。
そして、そのことがオランダ凋落の大きな原因にもなって来ます。
対して一方のイギリスにおいては、都市の商工業者、中産階級を基盤として議会の権利や民権の尊重を主張し、宗教的寛容・積極財政を採ったホイッグ党と王権・国教会を擁護して貴族・地主・聖職者の支持を受けたトーリー党が平和裏に交代して政権を運営していきます。
プロテスタントの要素、寛容の精神、そして初歩的ではあったものの民主主義から派生した結果的客観的評価システム である政権党の政治に対して多数の国民による選挙における支持率という評価と政権を任せる報酬というシステムによって、イギリスは世界覇権を確立していきます。
ヴィクトリア朝中期において、イギリス人は世界人口の2%でしかありませんでしたが、最先端業の生産設備では全世界の40%から45%を保有しており、世界の産業生産の実に4割を担っていました。
1860年頃には、世界の商船の1/3以上がイギリス国旗をはためかせており、イギリス海軍は保有する艦船数が多いこともあって、2位・3位・4位の国々の海軍を合わせたよりも強力でした。