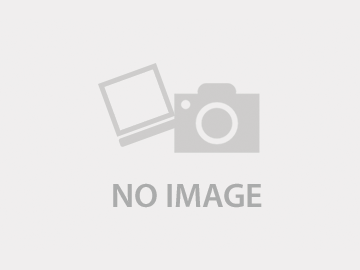なぜ1970から1980年代の日本の経済は最強だったのか?
そして、平成の失われた30年を経て、なぜ現在においては停滞し、没落してしまったのかを考証していきます。
現在では、米国のベンチャーはあらゆる分野でその勢いは留まるところを知らない活況を呈しています。
それに比べて日本のベンチャーの勢いの無さは対照的ともいえます。
しかし、1970 年代から 1980 年代にアメリカ経済が衰退傾向を強めた『アメリカの没落』といわれた 時代は、日本の製造業が世界を席巻していた時代でした。
その原因・要因を学びに日本を訪れていた米国の役人や知識層は、日本から学ぶべき大事な要素は『ベンチャー企業である、ベンチャーの起業家精神である』と現代の日本人には信じられないようなことを主張していきます。
「日本の産業が戦後こんなに強くなったのは、ソニー、ホンダ等の強力な急成長ベンチャー企業が誕生し、それまでおっとり構えていた松下電器、日立、東芝、トヨタ、日産等の大企業がソニー、ホンダが起こすイノベーションに負けてはいられない、と大企業とベンチャーの間で激しい競争が起こったから製造業の基盤全体が世界最高のレベルに持ち上げられたのだ。
それに比べて我が米国のGE、モトローラやGM、フォード等の大企業は、独占的な地位を享受して激しい競争が国内に無いから革新的なイノベーションが起きにくくなっている。日本の脅威に勝つためには米国でも日本のように強力なベンチャー企業の創出を真剣に考えなければならない」という内容でした。
日本が成功したように、米国でも強力なベンチャーが出てこないと大企業が停滞し、米国の産業復活はない、と思い詰めSBIR政策を進める法案を数年かけて、多くの反対を押し切ってエドワード・ケネディが中心となって議員立法化され1983年に発足します。
1983年から実施されたSBIRは、各省の外部委託研究開発予算の当初0.25%(現在は2.5%)を、ベンチャー企業に強制的に割り当てる法律に基づいているが、当初各省の大反対の中でとりあえず時限立法ということでスタートしました。
1970年代から1980年代にかけて躍進する日本への対抗策として、イノベーションを大企業に頼るだけではなく、ベンチャーの活力を生かそうとしたある熱心な官僚の意見をエドワード・ケネディが後押しして、やっとのことで法制化したものでした。
この法案に反対する各省の官僚は、例えば、ミサイルに関わるシミュレーションプログラムを、できたばかりで数人の従業員の会社に頼んでもそのベンチャー企業の信頼性は不明であり、税金を使ってそのようなリスクは取れない、と主張しました。
法制化され強制されてしまった後は仕方がないので、できもしないような難しく大企業が背を向けるような仕事をベンチャーに振り向けて、手も足も出ないとベンチャー企業にあきらめてもらおう、という作戦で難しいテーマを決めて公募してみましたが、いくつかのベンチャーがその難題を短期間にものの見事に解決していきます。
その様な経過を経て、SBIRはアメリカに定着していきます。
全米で毎年2千以上のベンチャーが資金援助される規模の大きさや、フェーズごとに練られた仕組みの良さや、多くの省が競い合って参加する仕組み等で成功するベンチャーが多く、長年続けられている政策であり、ベンチャー育成政策の成功例として世界的な注目を集めました。
このSBIR政策とほぼ時を同じくしてIT革命がおこり、米国のベンチャー活動は大きく動き出し、そこから生まれ続ける革新的なイノベーションは大企業を刺激するようになり、米国では「シリコンバレーモデル」が「国のビジネスモデル」であるとまで言われるようになりました。
ベトナム戦争以降の長い経済・社会の停滞・低迷を脱した後での、これらアメリカ経済の奇跡の復活はニューエコノミーと名付けられ、自信を取り戻したアメリカの人々の心に刻まれました。
次に、日本の戦後直後から振り返って見ます。
財閥解体・農地改革などの戦後改革により、公益に沿わない不健全な貧富の極端な差が改善され、健全な中間層の成長による需要力・購買力が増し、経済が国内市場の力によって、発展していきます。(これはレーガンノミクスでアメリカ経済が改善せず、中間層を重視したクリントノミクスが成功したことと共通します)
戦後の日本は改革の恩恵の飴玉を少しずつ舐めながら消費して、成長して来た感があります。
歯科矯正にしても、習癖の改善なく、また骨の裏打ちのない所に無理に拡大をした時、その後、顕著な後戻りが見られます。
日本における政治経済においても同様のことが見られます。
半分与えらた結果的客観的評価システムに裏打ちされた安定した民主主義のため、その有難みの大切さに実感がなく、また本質的な戦前の反省がされていない状態によって、戦前と同様に、安定した民主的コントロールつまり、結果的客観的評価システムによるコントロールが不十分な中で条件的客観的評価システムであるメリットシステムにより生み出された官僚の暴走が少しずつ復活して来ます。
前述した通り、国会のチェックがほとんどされない特別会計が全予算の八割方を占め、それによって裏打ちされた天下りの人事によって、公益性に反する利益を官僚機構が追及していきます。
天下り人事に伴って、受け入れ企業側への規制・補助などに関する利益供与の付随、非効率な外郭団体の存在により、自由競争が阻害され、無駄な財政支出が増大することによって、莫大な世界一の財政赤字国となっていきます。
戦後に撤廃された様々な不公平が少しずつ様々な分野で復活して来ます。
条件的客観的評価システムであるメリットシステムと密接に結びついている学歴の頂点にある東大の合格者の家庭の年収にしても、高度成長期には合格者の家庭の年収は平均年収より低かったのが、徐々に上がり、現在でははるかに高い世帯年収となっています。
歴史的に見て、後天的な差が出るのが健全で社会が発展し、先天的な差が出るのが不健全で機会の平等が成立していない証拠といえます。
アメリカの経済をリードするベンチャー企業のトップの多くはハングリー精神が旺盛な移民一世か二世であることを見ても、機械の平等つまり、公平性がしっかり担保されていれば、必然的に平均的には、低年収の家庭から成功者が出ることが多くなるといえます。
戦後改革によって、戦前と異なって、選挙による政権党の政治の評価、他の機関の干渉を受けないでの国民大多数による審判、政権党から選ばれた首相が実権を握って評価の対象となり、責任を持つ政策・政治が行える環境が整えられ、システム的には結果的客観的評価システムの裏打ちを得られる状況となりました。
しかし、日本の政治において、政党という存在は戦前の流れから、政治上の政策・主義の相違を前提に集まる政治団体という性質以上に、地縁的・職縁的に大同団結していく利権団体の性質の要素が強く、政治家は政策を学ぶよりも、年間何百回にも及ぶ新年会・結婚式・盆踊りの顔出しが重要視され、政治家になるのも利益団体を引き継いだ血縁的世襲された二世三世の政治家か、団体や建設会社などの利権導入を担う者、中央とのパイプ役としての官僚位で、例外的に知名度を利用したタレント議員などでした。
純粋に政策を学び、政治家を志す者を送り出す場として、一時期的に松下政経塾がありましたが、教育システム・カリキュラムなどが客観的評価システムに裏打ちされたものでなかったため、ただ籍を置いただけで立候補する者が続出し、廃れていきました。
政策通として担う役割を果たすべき官僚も戦前の時と同様に、政官財全般に渡る官僚閨閥図(戦後民主改革によって一時期的には、完全ではないにせよ、かなりの部分は取り除かれましたが)を戦後においても再形成し、政策通グループというよりも、利権グループの中枢的役割の要素が強いものでした。
日本の国勢選挙での投票率は半分程度しかありません。
それに対して、北欧諸国の投票率は高く、デンマークを例に出すと、国政選挙で90%程度をキープしています。
候補者も多く、議論点のいくつかの賛成・反対の選択によって、どの政党・候補者と自らの考え方が近いかを確認できるシステムもあります。
そして、二世議員という慣習もありません。
衆愚政治の原因には、選挙民が識字率が低かったり、無教養であったり、政治に興味を示さないことや選挙民に選択肢が少ないこと等があります。
選択肢が少ないと比較する評価ができないので客観的評価システムの機能が十分働きません。
客観的評価システムが機能しなければ、グループ主義的癒着が起きやすくなります。
そうなると、政府においても公益の為にベンチャーや起業を促進させるよりも、既得権益を守るために、既存の業界ルールをディスラプトするような新しいビジネスが生まれると、既存ビジネスを守るために規制したり、阻害する方向性に進んでしまうリスクが高くなってしまいます。
新しいビジネスモデルやサービスが生まれたときに、早い段階で規制してがんじがらめにしてしまい、結果的にその芽を潰してしまう様にです。
また、戦後日本においては、長きに渡り、年功序列制度導入されてきました。
年功序列が日本経済を支えてきたといっても過言ではありません。
勤続年数や年齢は、その人の能力を測るわかりやすい指標でもあり、長く勤務していたり年を重ねていったりすれば、自ずと経験やスキルは蓄積されていきます。
その結果、会社に対する貢献度も高くなると見込まれるため、そうした前提に立って勤続年数の長い年長者を優遇するというのが年功序列の本義です。
ある意味客観的評価システムの一種ともいえます。
しかし、裏を返せば成果を上げなくても年数や年齢で好待遇の身分を勝ち取れるということを意味し、実力はあっても若年者や勤続年数の短い人は、組織の序列のなかでは下の位置に組み込まれます。
そして、若手の人材が成果主義の企業や海外へ流出してしまうことにも繋がります。
また、年功序列における人事評価の対象は、勤続年数や年齢などが主です。成果に関してはそこまで重視されないだけに、社員のなかには成果を第一としない思考を持つ者も出てきてしまいます。ただ勤続年数や年齢を積み上げるだけで、成果を上げようという意欲が低下してしまえば、会社の業績にとっても良くない影響を及ぼしかねません。成果を評価基準にしない年功序列の仕組みでは、リスクを取ってまで大きな施策にチャレンジする必要がなく、企業や人材の成長性はどうしても薄れてしまいがちです
よって、余り、質の高い客観的評価システムとはとても言えません。
ただ、対比する欧米で主流の成果主義の制度が客観的評価システムという観点で見て、より質の低いレベルである状態の時代では、この年功序列制度は日本の経済を押し上げていく原動力ともなりました。
勤続年数や年齢以外の部分で人材を評価するのは簡単ではありません。評価が主観的なものに傾き、成果主義 が逆効果になってしまうことも多々あります。
その中では、年功序列における人事評価は評価が単純・簡単であり、少なくとも、ある程度の客観的評価システム的プラスの役割を果たすことができます。
きつくいってしまうとつまり、ないよりはましということですが・・・
それでも上手く機能せずに、一部の上司などの主観性によりマイナス的作用をしてしまうリスクが多く含まれるようなレベルにある成果主義よりは相対的に見るとかなり優れた制度とも言え、実際的に20世紀末期まではそのような状態の時代が続きました。
しかし、クリントン政権下でNPR 、国家業績評価という結果的客観的評価システムの一種を導入して、国家改造を行う過程において(詳しくは、こちら)、ベンチャー企業支援や IT 産業発展の環境整備がされ、そして IT 革命に代表される技術革新の進展により、さまざまなベンチャー企業が大きく成長し、アメリカ経済の体質が変わり、強いアメリカ経済が復活したという認識の下、ニューエコノミーという時代に入りると、成果主義の制度でも客観的評価システムという観点で優れたシステムを導入する企業が続発していきます。
結果的客観的評価システムの下、生まれた企業のためその傾向を示すのは、当然といえば当然かもしれません。
その代表的な企業が『ワーク・ルールズ!』で書かれている人事制度を採用しているGoogleです。
普通の会社であれば業績評価は上司のマネージャーが行いますが、Googleの業績評価は客観的な指標を持つために複数のマネージャーが合同に行います。
Googleではマネージャーと部下が仕事について発展的な対話をすることが求められています。
発展的な対話によって部下がマネージャーの心象を害すこともあるでしょう。
もしもGoogleの業績評価が客観的な評価ではなく、上司だけの評価であれば、上司への悪い印象は給料直結してしまいます。部下は上司に発言することを恐れることでしょう。
「発展的な対話が業績とは関係がない」と示すためにも、Googleでは、業績評価を複数のマネージャー合同で行います。
つまり、マイナス的一部の上司の主観性を排し、客観性を発展的な対話によってさらに高める努力がされているということです。
これらの企業の登場により、日本は低成長期に入ります。
その主たる原因はバブル崩壊というよりも、客観的評価システムという観点における年功序列制度の相対的価値の低下にあるといえます。
その証拠に、日本の企業の中でも少数ですが、客観的評価システムという観点において優れた人事制度を採用し、大きく成功している企業もあります。
その代表的な企業がキーエンスです。
日本が誇る超優良企業といえば、その筆頭に挙がるのはキーエンスです。
工場の自動化に不可欠なセンサー機器や画像処理機器などの開発から販売までを手がける。一般消費者との接点がないBtoBビジネスのため、知名度はそれほど高くありませんが、順調に成長を遂げ、日本の株価総額では3位or4位になります。
給与のランキングでも常に最上位に位置しています。
キーエンスでは、基本給を基準とした賞与とは別に、連結営業利益の一定割合を社員に支給する業績連動賞与の制度があることも、年収が高い理由です。
「業績連動型賞与制度」は、業績に対する従業員意識の向上、業績に応じた人件費の適正化、賞与決定プロセスの明確化・透明化などを目的として、導入されてます。
予め定められたルールや算定式に基づき、成果に応じて賞与が得られるので従業員にとってはわかりやすく、納得しやすい制度でしょう。そもそも、個人の成績だけでなく、会社全体の業績によるものが大きいので、経営参画意識を高める効果もあり、導入している企業も多くあります。
しかし、特筆すべきことはその度合と額です。
営業利益の10%が新卒社員を含む全社員に業績賞与として社員に還元され、分配されます(社員の頭数で割る)。
賞与だけで一千万円以上となる時も数多くあります。
これは正にシンガポールの官僚の給与と GDP と連動している結果的客観的評価システム(詳しくはこちら)と極めて類似しています。
また、後々、出世した人の共通点を探って採用活動に活かすために、採用面接でのやりとりの映像が録画され、分析対象になります。
この採用面接のフィードバックの大切さについては『ワーク・ルールズ!』の「第5章直観を信じてはいけない」でGoogleでも重視されていることが詳しく述べられています。
企業、国どんな組織においても客観的評価システムの観点における質の高さの必要性の重要度がこれらのことから実感できます。