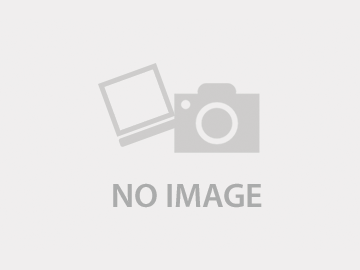記事の目次
①近代における二つの客観的評価システム
近代の欧米においては、民主主義の制度から派生した政権党の政治に対して多数の国民による選挙における支持率という評価と政権を任せる報酬という結果的客観的評価システム以外にもう一つ時代を変える客観的評価システムが登場しました。
それは、科挙の試験科目を儒学から西洋の近代学問に変えて、一般に公募された官僚を採用するための専門試験制度である資格任用制度、いわゆるメリットシステムです。
初めに導入したのは、ドイツの前身であるプロイセンで18世紀後半から導入されました。イギリス、フランス、アメリカ、日本などは19世紀後半に導入していきます。
先駆けて、この科挙よりも進化した条件的客観的評価システムを導入したプロイセンは、民主主義から派生した結果的客観的評価システムを欠きながらも、ヨーロッパ最強の近代国家の一つに躍進していきます。
日本においても明治維新後、このメリットシステムを導入し、富国強兵・殖産興業を推進し、アジア最強の近代国家となって行きます。
科挙にしても、メリットシステムにしても条件的客観的評価システムは、血統・血筋に依らない選抜の仕組みでコネや地盤のない人々にもチャンスを与えます。
しかし、結果的客観的評価システムのコントロールが働かない時、制度が一度定着すると、固定的で硬直化してしまう欠点があります。
科挙が、千年経ても、根本的改革がされず、より社会の利益、公益に沿ったメリットシステムを導入した欧米や日本に近代化において遅れを取り、植民地化されてしまったのもそのためです。
日本におけるメリットシステムにしても、戦前においては前述した通りに中途半端な民主主義により、結果的客観的評価システムは全く効かない状態のために、民主主義の欠点である猟官制度、政治利権などが噴出し、軍部を中心とした官僚の暴走を止められずに、内政に於いても、外交においても、破滅への道を進んで行ってしまいました。
近代においては、この二つのシステム(民主主義の制度から派生した結果的客観的評価システムとメリットシステム)を中心に、現代においては、他の客観的評価システムも交えて、世界各国の近現代史を客観的評価システムの観点から考察していきます。
②イギリスの近現代史を客観的評価システムの観点から考察
先ず、近現代史においては時代の先駆け的存在であったイギリスから見て行きます。
オランダから持ち込まれたプロテスタント的客観的要素や民主主義から派生した結果的客観的評価システムによって、世界一の超大国・覇権国となったイギリスでしたが、19世紀後半にかけて、アメリカ、ドイツに急速に追い上げを受け、国力的に相対的な重みが低下していきます。
1ジェントルマン資本主義
イギリス側の要因として、ジェントルマン資本主義というものがあります。
ジェントルマンとは、16世紀から20世紀初頭にかけての実質的なイギリスの支配階級であり、本来は土地に立脚した不労所得者でした。
その後、経済的に成功した富裕層が社会的な名誉を欲するようになり、ジェントルマンの仲間入りを果たそうとしましたが、その中でも銀行家や海運業者などは本人は働かないという点でジェントルマンに生活スタイルが近かったために、比較的容易にジェントルマンとして迎え入れられました。
ジェントルマン精神として、実利的なビジネスを敬遠し、製造業などの実業の軽視などがあげられています。
事実、20世紀後半まで、オクスフォード大学やケンブリッジ大学には工学部もビジネススクールもなく、卒業生はメーカーに就職するよりも証券会社・保険会社・銀行など金融関連の就職先を最良として選択していきました。
そのため、世界最初の産業革命国でありながら、産業資本主義は育たず、世界の工場であった期間は極短く、19世紀後半におけるイギリスの農業を除いたGDPの製造業の比率は三分の一以上あったものが、20世紀には10%台まで低下しています。
19世紀末には、イギリスの工業生産力が世界的に見て急速に低下していきます。
主として、アメリカやドイツの追い上げによるもので、1880年代にはアメリカに追い抜かれ、1900年代にはドイツに追い抜かれて行きます。
アメリカやドイツ側の要因はそれぞれの国々の近現代史の流れを見ていく時に後述していきます。
これらの製造工業などにおいて、イギリス以上に先進していく国々の登場により、イギリスは商品の取引、つまり貿易の収支は赤字になり、これを海運業のサービス及び資本輸出の利益など国際金融の黒字で補うことにより、全体として経常収支を黒字に保つようになっていきます。
ジェントルマンの条件は不労所得の流れを汲む、膨大な資産を有し、その資産を他人に貸し付けることによって、政治・チャリティー・文化活動を行う時間・資金を持つことです。同時に教養や知識も必要条件とされました。
彼らの存在のプラス面としては、彼らが、結果的客観的評価システムに裏打ちされた民主主義をイギリスが世界で初めて成立させることにおける大きな要因になったことなどが挙げられます。
衆愚政治に陥る大きな二つの要素として、一つには、①低識字率・教育制度の不備による国民の知識・判断能力の欠如があります。
そして、もう一つの大きな要素は、たとえ国民が的確な判断能力があったとしても、②選択する項目が少数であったり、選択するために与えられる適切な情報が少ないことです。
民主主義制度から派生し、そして、その民主主義自体を裏打ちすることによって安定した民主主義を初めて誕生させた政権党の政治に対して多数の国民による選挙における支持率という評価と政権を任せるという報酬という結果的客観的評価システムは、後者②における選択するための情報不足を大きく補う役割を持ちます。
しかし、民主主義が安定するまで、つまり民主主義から派生する結果的客観的評価システムの裏打ちを民主主義
自体が受けることができるまでの初期の段階においては、優先的に必要なことは前者①の国民・選挙民の判断能力の欠如を解決することになります。
初期の段階、まだ不安定な民主主義の段階においては、後者②の問題を解決するための民主主義から派生する結果的客観的評価システムが当然のことながら、存在しないためです。
民主主義は、民主主義から派生する結果的客観的評価システムの裏打ちを受けて初めて安定するからです。
イギリスは、初期の選挙権が与えられた者がジェントルマンなどのインテリ・知識層の少数に限定されており、識字率や教育制度の向上と供に、選挙権が徐々に拡大されていきました。
識字率が低い、初期の段階から普通選挙を実施したフランスでは衆愚政治により、なかなか安定した民主主義を構築することができませんでした。
対して、勃興した中流階級の上層部を体制内に取り込んだ上流階級のインテリ・知識層が、ノブレス・オブリージュの建前上、不労所得層特有の時間の余裕さから政治活動などの公益に関ることに専念できた人々、つまり貴族と上層部平民を含むジェントリから派生したジェントルマン層が、安定した民主主義を築く上において大きく寄与することによって、イギリスは世界で初の安定した民主主義を定着させます。
しかし、そのマイナス面として、上流階級は勿論、成功した中流階級も不労所得層・利子生活者階層を目標としたために、製造業などの産業資本家が育たず、産業イノベーションの停滞から国内投資も停滞し、代わって対外投資・資本輸出が急増し、海外からの巨額の利子・配当収入を得る利子生活者階層が増大し、帝国主義政策が1870年代以降加速した原因ともなりました。
19世紀初頭から中頃にかけて、まさに世界の工場として、イギリスが産業革命以来の圧倒的な工業力を維持している間は、植民地以外の国から安く原材料が輸入できて、植民地以外の国にも高く輸出が可能であったために、何の目的で無理して、植民地を維持しているのか、全くもって経済的必要性が皆無に近くなってきたために、自由貿易政策・帝国防衛費の削減・国際平和の維持・植民地分離論などの小英国主義の考え方が急速に普及していき、イギリスの帝国主義において一定の歯止めとなっていました。
しかし、1870年代以降、アメリカとドイツなどの世界市場進出に押されて、対欧米の国際収支において膨大な赤字を計上するようになると、その赤字を補填するために、イギリスの銀行家たちは世界各地の政府、鉱山やプランテーションに資金を供与して、その利子を稼ぐことになりました。
1870年代以降、急速に展開された帝国主義政策の主たる動機は、利子生活者階級の海外投資の安全を保障し、その利益を一層拡大することにありました。
イギリスの帝国主義政策により、世界最大に拡大された植民地経営は、本土の安定した民主主義などのシステムは導入されず、直接搾取するか、間接的に不平等条約などにより利益を吸い取るなど、不公平極まるものとなりました。
国内ではイギリスを世界一の超大国にしたシステムは、国外ではシステムが存在しないため、利益の追求目的に無秩序に行動がなされていきました。
イギリスの経済を支えたのは、インドのアヘンを売却し、莫大な利益を得るなど非人道的、民族的不公平なものでありました。
不公平な利益である以上、当然のことながらそれを奪い合う列強国間の植民地獲得競争が行われ、植民地サイドからも独立運動が起きました。
イギリスはセポイの反乱、南ア戦争、第一次世界対戦と莫大な戦費を抱えることになります。
特に第一次世界対戦における国力的ダメージは大きく、これを境目に、世界の覇権国たる地位はアメリカに移ったと言えます。
イギリスを世界の覇権国たる地位につけたのは、国内においてスコットランド人、ユダヤ教徒やユグノーなど少数派の国民に対しても、客観的要素・システムを持って、当時の標準に比較して、極めて公平な関係を築き上げることができたことが最大の要因と言えます。
そして、イギリスを覇権国から転落させた最大の要因は、国外、特に非白人植民地において、国内のシステムを運用せず、無秩序な利益を追求する不公平な搾取や偏見的・主観的行動方針を特に現地在住のイギリス人に許してしまったために、世界的な対立・争いの害が国内とはまさに対照的にのしかかり、イギリスを衰退させてしまったことにあると言えます。
封建的または独裁的国家においては、既に強固な政権側・体制側のグループ主義が根付いてしまっているため、これを解除するには、Ⓐ外部、つまりすでに民主化された外国からの経済的・地域的・武力的影響もしくは、Ⓑその強固なグループ主義に対抗できる別のグループ主義がなければ非常に困難で、不可能に近いものがあります。
人は集団化の傾向の強い動物のため、いくら優れた社会的システムを提言したとしても、グループ団結を強く誘引する利益的・他排的なものがなければ、そのシステムに賛同する者が多くとも前進しないと言うことです。
イギリスは、世界初の安定した民主主義国家を確立した国です。
よって当時、確立するまでは当然、Ⓐ外国からの誘引は期待できず、絶対王政の何重ものグループ主義と対立することになり、決してどんなに優れた個であっても対抗は不可能であり、それらに対抗するためのⒷ別のグループ主義が不可欠でした。
支配層の移行の流れを宗教的要素でみると、カトリックからイギリス国教会への流れ、経済的・階級的要素でみると、貴族階級からジェントルマン層への流れとなります。
カトリックとプロテスタントの中間的性質があるのが国教会であり、貴族階級をより流動的・拡大的にしたのがジェントリー由来のジェントルマン層です。
一次民主革命のピューリタン革命(カルヴァン派的プロテスタントが主体)では、 普通選挙導入も含む急進的なものでしたが、結局は強固なグループ主義が築けなかったため、旧来の貴族層カトリック的な王政復古がなされました。
二次民主革命である名誉革命(国教会が主体)では、一次の時のように、王制を廃止せずに、立憲王政という妥協的な体制を採り、封建的特権の廃止なども徹底して行いませんでした。
旧来の貴族階級を取り込む形で、ジェントルマン層による不完全ともいえる市民革命となり、一次革命の主体となったカルヴァン派的プロテスタントの多くは既存のグループ主義の存在しないアメリカなどに移住して行きました。
(既存のカトリック・旧来の固定的な 少数の世襲的・貴族階級的なグループ主義)➡(国教会・比較して流動的で拡大された新貴族層であるジェントルマン層によるグループ主義)に移行していきました。
その過程で、安定的な民主主義が構築されていきます。一方で、いきなり普通選挙導入による民主主義を目指したフランスは国内外のグループ主義の抵抗を受け、安定した民主主義の定着は同時期においては不可能でした。
こうした世界初の安定した民主主義を達成したイギリスでしたが、その代償としてはジェントルマンなどの不労所得層を指向する負の作用の影響を受けたり、アメリカなどのプロテスタントに特化した国家に比較すると、プロテスタントの 客観性などにおける経済・社会システムに対する 恩恵が少なくなりました。
工業・製造業などの実業を軽視する傾向は、イギリス経済の特徴となってしまい、イギリスが再度、一流国となる際の大きな足かせとなっていきます。
また、これらの階層間の分離が普通選挙後の労働組合の暴走を生み、英国病、ヨーロッパの病人と言われる状態に陥ってしまいます。
北欧では、プロテスタント的平等指向により、階層格差が小さく、教育も全体的に行き渡り、教育レベルが高いためか、労働組合は賃金のベースアップを求めるだけでなく、独自のシンクタンクなども持ち、場合によっては賃下げや増税政策を提言し、ワークシェアやはフレクシキュリティを実行する側面を持ちます。
2労働組合によるグループ主義
しかし、第二次世界対戦後のイギリスにおいては、階級格差・教育格差も大きく、その中で荒廃した基幹産業を労働党政権は国有化して行きますが、その基幹産業の労働組合が国のインフラを支配して、ストを多発して大幅賃上げをもぎ取り、二桁以上のコスト・プッシュ・インフレを引き起こします。
国民の勤労意欲も内外の投資意欲も減退し、英国病という経済停滞に陥り、1976年には財政破綻し、 IMF(国際通貨基金) から融資を受ける羽目にまでになりました。
選挙権が拡大されることにより、(ジェントルマン層のグループ主義)➡(労働組合によるグループ主義)に徐々に移行していき、それらの労働組合はクローズドショップ制により、組合幹部が組合員に対して大きな権力を持ち、ピケッティングや非公式ストなどを繰り返し、非民主的な管理状態で、グループ主義を追求していきました。
しかも、1981年には労働党党首選において、半分に近い票を組合票と定め、公(おおやけ)の政党をも非民主化したグループ主義が暴走して、勢力下に治めようとしていきます。
そのグループ主義の暴走を止めたのが、民主主義から派生した結果的客観的評価システムです。
これらの労働組合に牛耳られた労働党の行う政権に対して、国民の大多数による得票率という評価が低下して、その結果政権を失いました。
3サッチャーによる大改革
労働党に代わり、保守党のサッチャーによる大改革が行われました。
ストを行う場合は組合の投票による決議を必要とし、非公式ストの場合は組合員費の支出は凍結できるように法律を改定し、労働組合の民主化を進めました。
固有企業を民営化し、減税や規制緩和を行い、市場原理・利潤原理を取り入れて、経済の再建を目指しました。
しかし、不況は改善されず、失業者数はむしろ増加し、財政支出も減りませんでした。
それは至って当然とも言える結果でした。
アダム・スミスの古典的な理論に戻っただけで、元来、資本主義自体には元々強固な客観的評価システムの作用・機能は有りません。
それを補うために、民主主義から派生した結果的客観的評価システムの作用・機能を包有する政府のコントロールが必要とされてきますが、これらが戦後のイギリスのように、非民主的になってしまった労働組合に支配されたり、同様に日本の官僚の暴走によって生み出された、非民主主義的である特別会計の問題などが生じると、民主主義から派生した結果的客観的評価システムのコントロールの作用・機能が正常に働かない状態となってしまいます。
かといって、政府のコントロールを取っても、以前のような資本主義オンリーの、客観的評価システムのほとんど効かない状態に逆戻りするだけで、問題は全く解決しません。
大きな政府と言われていても、民主主義から派生した結果的客観的評価システムが正常に機能している北欧諸国や独自の結果的客観的評価システムを適切に作用させているシンガポールにおいては、それらの問題点はほぼ解決されています。
実際、イギリスが英国病から脱出し始めるのは、サッチャー政権ではなく、メジャー政権からでした。
4数値指標による業績管理という結果的客観的評価システムの導入
メジャー政権では、数値指標による業績管理という結果的客観的評価システムの導入がなされて行きます。
政策立案以外の執行部門の委託を受けたエージェンシーに対して、契約した結果が出なければ賠償責任を負わせ、出れば結果に合わせて報酬を与える結果的客観的評価システムです。
これによって、先進国中一人当たり GDP が最下位であったイギリスは、過去最長期間における安定成長を続け、上位に返り咲くことになります。
しかし、公共セクターの報酬は民間セクターに比べて、上層の職務ほど低くなっており、シンガポールなどと比較して、インセンティブが低く、優秀な人材が民間に流れたり、もしくは便宜供与を目的とする民間からの転入などもしばしば見られました。
加えて、製造業などの実業を軽視し、本来裏方であるべき金融業に依存した産業構造の改善も進みませんでした。
物理学などを学ぶ学生がいなくなり、金融機関への就職を目指して学ぶ学生が増え、製造業におけるイギリス人の技能不足がさらに深刻化しました。
それらを補うために、外国人労働者や移民がその人材需要のギャップを埋めるようになりましたが、それに対しても移民反対の動きから EU を離脱するなど諸問題が続出しました。
しかし、昔の超大国として先頭を走ることはなくとも、少なくとも二流・三流国との評価やヨーロッパの病人としての立場は完全に脱することには成功しました。
他国の影響を介さない場合、別のグループ主義の力を頼らないと既存の強固なグループ主義を壊すことはできません。
しかし、新しい別のグループ主義の力を借りると改革は変質してしまいます。
このパラドックスを覆すには客観的評価システムが極めて有効であることはイギリスの近現代史を見ればわかります。