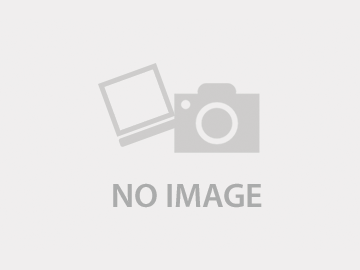基本、対立・紛争のない方が良いのはいうまでもありません。
今の日本の様に曲がりなりにも安定した民主主義下にあり、武力的抑圧を受けていない状況下で武力的改革をアプローチすることはまさにテロ的行為といえます。
しかし、江戸時代やフランスの絶対王政のような封建時代の武力的抑圧下の明治維新・フランス革命や見せかけの民主主義で実際は治安維持法などファシズム独裁の武力的抑圧下にあった戦前日本のような状況下では、現実的にその武力的抑圧を解除するには武力的改革をアプローチするしか当時においては選択肢がないともいえます。
ただ、急激な改革・革命のときには、凄まじい対立・紛争により、結局all-loser(全員失う)の状態(少なくとも、一時期的には)になるリスクが極めて高くなります。
フランス革命しかり、共産主義革命しかりです。
よって極力避けれるものは避けるべきといえます。
民主革命を選択した坂本龍馬や北一輝にしても極力対立、紛争を避ける努力をしています。
坂本龍馬は戊辰戦争、北一輝は2,26事件の決起や日中戦争を起点とする太平洋戦争においてそれを避けるために身を粉にして、命懸けで奔走しています。
坂本龍馬の努力虚しく、戊辰戦争は勃発してしまいましたが、西郷隆盛と勝海舟の会談による江戸城無血開城によって、当初の予測されていたより小規模の内戦(それによって死の商人のグラバーが破産する程)となりました。
そうでなくもっと内戦が激化していれば、西欧列国がインドや中国の内戦を利用して植民地化やその維持に繋げた様に、日本も植民地化されていた可能性が十分にあります。
やはり、いくら民主主義など公益に大きく関与する大改革をするためにしても、対立・紛争が極力ない方が良いといえます。
対立・紛争が激化してしまう責任・要因は大きく分けて二つあります。
一つには、既存体制・既得権益サイドの執拗な抵抗です。
フランス革命を題材に見ていきます。
フランス革命直前においてのフランスのブルボン王朝が放漫財政を踏襲したことで破産に近づいた当時の国家財政の歳入は5億リーブルほどであり、実にその歳入の9倍の赤字を当時抱えていました。
1774年にテュルゴーが財務長官に任命され、財政改革を行おうとしました。
第三身分からはすでにこれ以上増税しようがないほどの税を徴収していたため、テュルゴーは聖職層と貴族階級の特権を制限して財政改革を行おうとしましてたが、既存体制・既得権益サイドの貴族達は猛反発し、テュルゴーは十分な改革を行えないまま1776年に財務長官を辞任します。
次に銀行家ネッケルが財務長官に任命されました。
ネッケルは免税特権の廃止によって税務の改善を図りましたが、三部会(前述の聖職者300人、貴族300人、庶民600人の三つの身分代表者によるフランス国内の全身分の部会による議会)での聖職者と貴族の特権身分による反対にあってやはり挫折し、1781年に罷免されました。
ネッケルの後任財務長官たちも課税を実現しようとしましたが(1783年、カロンヌ - 1785年、ブリエンヌ)、特に既存体制・既得権益サイドの貴族階級の抵抗で辞職に追い込まれ、財務総監官邸は「免職ホテル」と呼ばれました。
結局、破局的結末を迎え、特権階級・既得権益の人々はもちろん全ての階級の人々が激しい争い・混沌の中に陥っていきます。
もう一つは改革側の主観的暴走です。
これはある意味では既存体制・既得権益サイドの執拗な抵抗とセットで考えるべきことかもしれません。
既存体制・既得権益サイドの執拗な抵抗、それに伴う武力的圧政が強い程それを取り除くには、それに対抗する所の武力そして、それを構築するための主観的グループ主義が必要となって来るからです。
このことを封建制度から民主主義制度に移行する過程を題材に見ていきます。
西欧において民主国家と地理的・経済的・社会的に密接に交流・関係し、影響を受けている国や台湾の様に中国からの強い脅威に対抗するため民主国家(アメリカ)の意向に強く影響をうけたり、戦後日本やドイツのように民主国家に間接または直接的に統治を受けたりするいわゆる外的要因を主とするのではなく、各国が独自の内的要因を主として、封建制度から民主主義制度に移行する過程は大きく分けて三つあります。
一つ目はⒶカルバン派諸国のように新しい強固なグループ主義の移行によって行われるものです。
二つ目はⒷルター派諸国のように他国の成功例の影響によって、君主と国民が協調的に実施していくものです。
最後三つ目は、©共同体の概念によって、共産主義的平等主義傾向の強い急進的な動きにより行われるものです。
最後のものは、何とか共産主義国家の成立から免れなくてはなりません。
三つの中では、対立・紛争が極力少ない二つ目が良いといえます。
しかし、二つ目が成立するためには、ルター派諸国のように、民主主義の基盤となる各個人の判断による決定(自決思想)などの考え方が根付いている環境下において、下からの要求に対し、上が協力的もしくは強く反抗しない対応をしていく要素が必要となります。
王太子時代、農奴制廃止など広範な自由主義改革を行ったデンマーク王のフレデリク6世
同じくデンマーク王で革新勢力に好意を寄せ、内閣の組閣を命じ、義務教育改革や軍事費の削減などに注力したクリスチャン9世
協調的で民主的であり、その治世において身分制代表議会廃止と地方自治制、民主主義が全ての面で大きく進行したスウェーデン王であるカール15世
などが代表的であります。
それらの要素がない場合は一つ目や三つ目のように新しい強固なグループ主義の移行によって行われる形となります。(三つ目の共産主義も無産階級を主とするグループ主義といえます。旧グループ主義を破壊する作用においては共通します。ただ、少し違うのは、その後の主導権を握るのは彼らではなく、凄まじい内紛の環境下の中、特権化していく官僚組織ですが・・・)
このグループ主義の移行には当然のことながら対立・紛争が伴ってきます。
よって、対立・紛争を極力少ないものとするには、自決思想から導かれる客観性が重視される社会的土壌が必要不可欠といえます。
自決思想と客観性は密接に関連しています。
他決思想は他者に考え・判断を委ねるもので、反対に自分自身で判断していくのが自決思想です。
万人祭司の考え方からプロテスタントは自決思想と言え、教皇無謬説のカトリックなど大体の宗教は他決思想と言えます。
ケネディ大統領が就任演説で「あなたの国があなたのため に何ができるかを問うのではなく、あなたがあなたの国のために何ができるのかを問うてほしい」と述べたましたが、この言葉はまさに自決思想を指しています。
違う表現としては、カラマ・スッタでのブッダの言葉で『人から聞いたというだけの理由で信じてはいけない。何事も教師や司祭の権限だけの理由で信じてはいけない。ただ、よく吟味・熟考した上で、理性と経験によって、承認できること・良いこと・自他共にまた世界全体に恩恵をもたらすことを真実であると受け入れ、その真実に則ってあなたの人生を送りなさい。』というものもあります。
ミクロ的に個々が一人一人の経験と理性の下に吟味・熟考した意思や考え方をしっかり持つことによってそれらが交差・修正・補填し合うことによって、初めて客観性が生まれます。
大多数の人々が一つの考え方・思想に考えを委ねてしまうと(その方が正直、楽であり、恍惚感・安泰化感を感じます。全て、その提唱者の言葉のままに動けば良く、何より悩まなくてもするからです。)、マクロ的には健全な客観性が形成されず、主観性が幅を利かすことに繋がります。