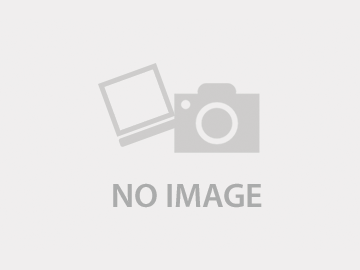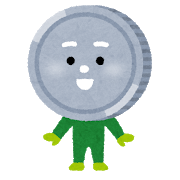北一輝というとファシズム、社会主義者というイメージが一般的歴史的通説です。
ただ歴史的通説が全て正しいというのは幻想であることが、この本を読んで本当に実感しました。
歴史における通説というのは総じて、勝者の論理、当時の社会的強者、体制サイドの主観的なフィルターによって歪められてしまう傾向にあるのが残念ながら世の常といえます。
2,26事件における田中勝中尉の『自分は北らの思想に染まって、民主革命を成さんとしたものではありません』という証言をみても、戦前のファシズム体制下では民主主義者として非難されていますが、戦後民主主義体制下ではなぜか逆にファシズムの象徴として黒を白、白を黒とする様なご都合主義の矛盾した非難ありきの非難がされています。
日本改造法案大綱を見ても、基本的人権の尊重、貴族院・華族制廃止などの階級制度の無用論、言論の自由、農地改革、財閥解体、女性の人権保護を唱え、また共産党と違い私有財産・宗教の自由も認めており、まさに戦後民主主義の雛形と言える内容です。
特に私有財産、民主的個人の重要性・必要性は強調され、これらが尊重されない社会は中世の奴隷的封建時代に他ならないと述べられています。
私有財産や私的企業の資本金上限額を設定したのも、それらを否定したのではなく、国民自由の人権は生産的活動の自由において表われるので特に保護助長されるべきと述べられています。
上限基準も当時の価値で見るとかなり高額でほとんどの個人・企業はその経済的自由を謳歌できる制限設定でした。
なぜ、その様な制限設定をしたのかというと、ひとえに国益を大きく損ねるだけでなく、帝国主義を強力に裏打ちすることにより世界的公益を大きく損ねている財閥支配を制限するためでした。
当時の財閥支配の弊害の凄まじさは、現在のフィリピンや韓国を見ても、少し覗うことができます。(当時は、帝国主義全盛の時代の為にはるかにさらに大規模なものでしたが)
北の記している社会主義とは、現在において一般的に意味されている狭義の共産主義的意味合いのものではなく、政府の介入を積極的に行う現在の民主国家のほとんどが属するところの広義の社会主義に他ならないことが、この本を読めば読むほど実感できます。(狭義の社会主義と広義の社会主義についての詳細についてはこちらに)
北は天皇を神聖視せず、万世一系は未開国の思想としながら、共産党の様に打倒対象と考えず、天皇は国民に近い家族の様な大切な存在という戦後の象徴天皇制に類似する国民の天皇という考え方を二十歳にして新聞にて発表します。
当時の天皇の国民とした天皇制を容認していた美濃部達吉や吉野作造と比べても民主主義的であり、美濃部達吉の天皇機関説よりも北一輝の考え方の方が戦後の象徴天皇制に近いといえます。
2,26事件において、民間人を担当していた吉田裁判長が『北一輝は2,26事件に直接責任がないので不起訴ないし軽刑』と主張してる中で、軍部上層部の寺内陸相が『北は極刑にすべきである。北は証拠の有無に関わらず、黒幕である』と極刑の判決を強要することにより冤罪で国賊として死刑宣告されている身になりますが、『たとえ、三ヶ月でも良いから、ここから出してくれたら、中国に渡り、蒋介石政権と日本の間の話をつけてこられるのだが…その後で、私は戻って来て死刑になるよ。それができないのが心残りである』と最後まで公益を考えて亡くなります。
北は昭和七年に『対外国策に関する建白書』で、「日米戦争は必ず英米露支対日本の戦争つまり世界全体とする戦争となるから、これをしてはならない」と戒め、、三年後の日米合同対支財団の提議の建白書では、日米戦争は支那を問題とする形で勃発すると予言しています。
その対策に2,26事件直前は北は事件に関与するどころか、辛亥革命時の盟友である張群が蒋介石政権の外交部長の地位に就いていたことから、日中和解に自ら乗り出さんと重光外務次官とも長時間協議し、広田外相や代議士の永井柳太郎とも渡支の時期について相談して、三月の予定にしていました。
直前になって、青年将校が決起することを伝えられた北は内心では時期ではなく、国際間の調整より始めるべきかと思い、その行動に困惑しつつも、かれらへの情宜を捨てられず、同意を与え、事件の収拾策としての真崎大将に一任の助言(真崎大将に一任させれば青年将校をむざむざ犠牲にすることはあるまいと考えての助言だったそうですが、真崎大将は青年将校を切り捨てていきます。)などをしていきます。
それらに関する責任を北は重く考え、青年将校に殉じていきます。
ファシズムといえば、当時の体制側の一角を占めた統制派こそがそれに位置していました。
彼らが出した陸軍パンフレットの内容には『戦いは創造の父、文化の母』であると書かれ、尽忠報国の精神に徹底し、国家の生成発展のため、自己滅却の精神を育み、国家を無視する国際主義・個人主義・自由主義思想を排除し、真に挙国一致の精神に統一することなど、まさに軍国主義・ファシズム的なものでした。
日本改造法案の言論の自由、基本的人権の尊重、刑事被告人の人権保障、被告が無罪となった際の国家賠償制度の確立、治安維持法の廃止、普通選挙、象徴天皇制、近隣諸国の権利の重視、個性の伸張を力説した個人主義、障害者・児童・労働者など社会的弱者への権利保護・援助などの内容とはまさに正反対の内容でした。
北自身、陸パンの内容は財閥と妥協せる国家社会主義的色彩濃厚で、自身の改造法案の内容が一向に察知できなかったと述べています。
陸軍内部では皇道派は現場叩き上げ、統制派は高級官僚の事務エリートとされていますが、統制派はかねてより皇道派の軍事クーデター勃発を誘導させ、その鎮圧過程を逆手にとり、自分達の国家社会主義的ファシズム体制を確立させようとカウンタークーデターの構想を練っていました。
2,26事件の二年前に作成された対策要綱にそれは見て取れます。
2,26事件の青年将校であった安藤大尉の遺書にも、『自分達を犠牲に、虐殺して、自分達の行動を利用して、軍部独裁のファッショ的改革がなされようとしている。逆賊の汚名の下に虐殺され、これでは死に切れない。』と書かれています。
これらには宮中グループの木戸幸一なども絡んでおり、事件の一ヶ月前には既に既成事項として情報は回っており、元老の西園寺公望も前もって避難していました。
その後、陸軍統制派は事件処理に名を借りて、着々と軍部独裁のファシズム体制を確立していきます。
しかし、そのファシズム体制は連合国によって倒されます。
そして、改造法案に沿った戦後民主主義改革が行われますが、戦前においてファシズム体制に反する民主主義者として処刑された北は戦後において、なぜか再評価されるどころか、ファシズムの教祖とされてしまいます。
統制派が組み立てたファシズムと北の改造法案の類似点を敢えて探したとしても、対外政策におけることと資本の国家による干渉か又は規制位ですが、それらであっても質的には全く異なるものでした。
改造法案の対外政策を先ず見ていくと、『植民地であった朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできないが、国民としての地位は平等でなければならず、政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が実施される、将来獲得する領土についても文化水準によって民族に関わらず市民権を保証する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範になることができる。』というものでした。
当時の帝国主義万能の時代、ほとんど国が植民地支配を受けるか、さもなくば植民地支配をするかの時代でした。
第二次世界大戦後、脱植民地化が世界的に進行した時点での視点で見ると、独立を認めないことだけでも、帝国主義的・ファシズム的に見られるかもせれませんが、当時の弱肉強食の時代、弱者の国となると、人口が半減する程に搾取されたり、ホロコーストを受けたりするのが、決して珍しくない時代の視点で見ると全く変わって来ます。
陸軍パンフレットをほとんどの新聞が賛成し、穏健的、民本主義者で植民地国に同情的と見られていた吉野作造でさえ、朝鮮独立を認めておらず、日本の中国における権益を固守すべきで、日本が中国に出した二十一ヶ条要求に対しても賛成するような状態で、それに反する者は非国民と責められる様な時代でもありました。
その状況下でも、北は二十一ヶ条要求を鋭く批判し、日本に来ていた中国の革命派の譚人鳳を大隈重信と会見させて、彼らの見解を直接日本政府に伝えるための援助をしています。
また北の改造法案は朝鮮の独立を公言してはいませんでしたが、朝鮮の独立を希求する人々にとって、朝鮮の独立問題を曲がりなりにも採り上げている、ほとんど唯一の思想でもありました。
北は日韓の合併という本来的な趣旨に照らして、この合併は韓国併合でも併呑でもなく、対等の合併であるべきと主張しています。
そして、朝鮮は日本の属邦、植民地ではなく、その地位は内地と平等でなければならず、日本内地と同一なる行政法の下に置き、日本の一行政区として北海道と等しく西海道とせねばならないとしています。
その上で、現下の朝鮮政策を『甚だしく英国の植民政策を模倣したるが故に、根本精神からして日韓合併の天道に反するものであり、東洋拓殖会社が英国の東インド会社の統治を真似て植民地経営したり、日本の資本家が官憲と結託して土地財産を奪い民衆の生活を不安に陥れ、その不満を憲兵政治で抑えたりすることがまさに悪模倣にある。』と指摘します。
『日本が行うべきことは父兄的愛情をもって、朝鮮民族の覚醒的成長を促進すること』で、具体案として『十年後より地方自治制を実施して参政権の運用に慣習せしめ、二十年後に完全に日本人と同じ参政権を与える』としています。
朝鮮人の中には戦前の日本で朝鮮独立問題をまともに考慮してくれていたのは、ただ北一輝がいただけという思いを持っている者もおり、関東大震災の折の朝鮮人虐殺事件の時、独立運動家の朴烈が北の所に逃げ込み、助けを請うということがあり、北はここも監視されいて危ないからと、当座のお金を渡し、朴を逃がしています。
このことから窺われるのは、北は朝鮮の独立闘争に同情していたということを日本の当局や朴烈ら朝鮮人が知っていたということです。
戦後も、こうした心理はしばらく引き継がれ、在日朝鮮人の中には、関東大震災の様な出来事が起きたら、北一輝の様な人物の所に隠れようと、但し、現在にも北一輝の様な人物がいると仮定すればだがという言動も残されています。
また、中国に対しても、北は中国人以上に中国の立場を考慮・行動し、中国の利権を日米ソに次々に切り売りしている孫文を売国奴とまで批判し、辛亥革命の孫文と並ぶ両巨頭の一人である宋教仁が、清朝政府に利することになったとしても中国の主権・領土を守るために、間島問題における国境交渉に積極的に介入し、寄与したことについては逆に大きく評価しています。
北一輝は、中国における民主革命である辛亥革命に命を懸けて支援し、宋教仁の唯一無二の理解者で親友でもありました。
また、辛亥革命の重鎮であった譚人鳳の孫を大輝と命名、養子とし、溺愛します。大輝の母は産褥熱で亡くなり、父は反北京政府の活動で獄に繋がれ、脱獄を試みて銃殺されました。
一年二か月の赤ん坊は病弱のために骨と皮ばかりに痩せ衰え、この世のものとは思えなかった状態でした。
譚人鳳は日華両国のため、東洋永遠平和のために彼を養育してほしいと頼み込み、北は引き受けます。
その他にも辛亥革命の若き運動家の面倒をよく見、その中の一人に2,26事件時、中華民国外交部長であった張群がいます。
張群は北を頼って日本に亡命して来た一人で、北の墓の揮毫者でもあります。
戦後、中華民国(台湾)の代表として国賓待遇で来日した時は、北一輝夫人の住んでいる貧民窟を訪ね、北の位牌に線香を手向けています。
当時の時代の視点で見ると北は日本全国民の平均値よりはるかに非帝国主義的であり、石橋湛山の存在を考えると最も非帝国主義的とは言えなくとも、かなり非帝国主義的であり、当時の置かれている帝国主義的な環境下で、理想主義でなく、現実主義的な物差しで見ると、最も非帝国主義的と言えるかもしれません。
そもそも、北が改造法案を執筆した背景には、五・四運動の全支那に渦巻く排日運動の鬨の声が鳴り響く状況下にあり、原案が書かれたのも日本ではなく、上海でした。
北の中国における命懸けの活動の目的は英露を中心とする植民地化・分割政策から中国を守り、独立を目指す勢力を援助することにありました。
しかし、中国で日本の帝国主義的な対中政策を身をもって実感した北は、天皇の取り巻きである重臣・官僚・財閥・軍閥の複合体こそが日本の民主主義革命並びに中国革命の進展に立ちはだかる反動勢力であり、これらを打倒し、侵略と経済的略奪を行わずに、他国の民主革命を支援できる民主国家に日本がなり、植民地大国となっているイギリス・ロシアとの軍事的対決も辞さない日本を創ることが必要不可欠と考えていました。
帝国主義的大国であるイギリス・ロシアによって不当に抑圧されている外国の民族を開放する為に戦い、領土を取得することを北は主張しています。
但し、新領土では土着人を指令官として行政に当たらせるべきとし、西欧列強のような収奪主義的な統治でなく、民族に関わらず、人権を保障し、人種主義を廃して、諸民族の平等主義の理念を確立して、世界平和の規範を打ち出さなければならないとしています。
北が意図していたのは、古代ローマの最盛期、五賢帝時代のように、属州出身が皇帝になったり、近代イギリスの内地においてのスコットランド人が自由に栄達し、イギリス帝国はスコットランド帝国と呼んだ方が正確だと言われる程に活躍したような寛容と公平の実践であり、日本改造法案の改革つまり、日本の戦後民主改革のような改革を浸透させながら、地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認めていくというものであり、イギリスがカナダに対して行った対等のパートナー的対応と類似しています。
イギリスが世界の覇権国と成れたのは、スコットランド、カナダなどの白人人口が多数を占める国に対してはグループ主義(この場合は民族主義)に流されることなく、公平性と寛容の精神によって統治したことが大きな要因であり、覇権国から転落した要因の大きなものの一つとして、非白人植民地に対してはグループ主義(民族主義)に流されてしまって、不公平と不寛容の種を播いてしまったことがあります。
北は世界の全ての異なる民族にも公平と寛容の原則によって行くべしという思想であり、日本が世界の王者となるべきとしたのも、非白人国に対して西欧列強が従来的に行った搾取的圧政をもってなるべしとしたのではなく、寛容と公平の原則により成長して戦後は民主政治の普及を前面にパクス・アメリカーナによって、イギリスと入れ替わり、世界の覇権国になったアメリカ的なものに少し類似点があるといえます。(但し、戦後、アメリカはしばらくの間は日本の戦後民主化を助け、その成功を持って、韓国や台湾にも農地改革などを進行させようとし、建前上と同じ行動を取っていましたが、アイゼンハワー政権においてダレス兄弟が影響力を持つことによって、方向性は一変し、 多国籍企業が一人勝ちする、資本主義放任主義から生まれた帝国主義を彷彿とさせる新植民地主義的政策にシフトチェンジして行きます。)
実際的に世界的な西欧列強に対しての脱植民地化や日本の戦前体制から戦後民主主義体制への変換は両方とも武力的アプローチが必要であったことは歴史が証明していますが、吉野作造より八年早く普通選挙論を著作で中核的議論にし、普選論の先駆の一人であり、民主主義者であった北が民主的革命や武力によって西欧列強に対抗していくことを合理化していくようになったのも現実主義者たる由縁だったと思われます。
戦後、脱植民地化が進んだのも、北一輝や宮崎滔天の様な日本人が多数、命を省みず、経済的・軍事的にも支援したことが大きく関与しており、極めつけは望ましくない戦争で、統制派が指揮した帝国主義的な戦争であったにしろ、西欧列強を追い出し、また日本も敗戦を迎えたことによる植民地支配の空白状態を利用しての今まで多数の日本人によって支援され、準備された原住民の独自の軍隊による独立戦争が引き起こされたことが大きく、それによって西欧列強も経済的利益が保てなく撤退して行くことになります。
ここで初めて、石橋湛山の植民地経営は経済的に合わないとする理論が適合することになりますが、それはあくまで武力的アプローチが介在した上で成立したものと言えます。
次に資本の国家による干渉・規制の問題に移ります。
対外政策における統制派や宮中グループが組み立てたファシズム的なものと北の改造法案の内容が質的には全く異なるものであった様に、これらに関しても全く同じことが当て嵌まります。
国家が企業の経済活動に一切関与しない純粋な資本主義が成立することが困難であることを世界恐慌を経て、各国が認識し始める時代でした。
そのまま自由にしてしまうと、利益を追求する余り、過剰な生産などから深刻な恐慌が起こってしまうからです。
資本主義のシステムは、客観的評価システムの観点から見ると、評価するするための極めて有効なアイテムでは在りますが、それ自体は客観的評価システムの一種ではなく、たとえその様に規定したとしても、極めて初歩的なものといえます。
貨幣経済やそれは発展した資本主義のシステムがなければ、客観的評価システムの評価・報酬が土地や身分・特権階級など硬直的なものに限定されてしまいます。
また、資本的利益を上げることが社会の利益にイコールかと言えば、そうではなく、資本の利益のみを追及したが為に、独占資本などによる帝国主義的な侵略・戦争、過剰生産などによる深刻な恐慌、現代においては最も懸念されている環境破壊などの大きな問題が続出しています。
資本主義のシステムは他の客観的評価システムを十分に機能させるために必要不可欠なものではありますが、それ自体に十分な客観的評価システム機能がないため、資本主義経済を管理するための他の客観的評価システムの存在も必要不可欠となります。
各国はその管理を政府・国家が積極的に行うようにしていきます。
つまり、国家による資本の干渉・規制が機能する混合経済・修正資本主義というものです。
しかし、その管理を行う政府に客観的評価システムが波及していなければ、当然に資本主義経済にも波及しない形となります。
民主主義から派生し、そしてその民主主義を安定に導く結果的客観的評価システムはソ連やナチス、戦前日本のような独裁国家下では原則的には機能しません。
また、たとえ安定した民主国とされていても、客観的評価システムの機能が不十分な国では、官僚の暴走、無駄使いを起因とした財政赤字の問題が大きく浮上して来ます。
この際、政府の大きい・小さいの問題よりも、客観的評価システムの機能が十分かどうかが重要となります。
機能が優れていると、逆に大きな政府の方が財政赤字が少なくなります。スゥエーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランドなど北欧諸国は公務員数が多く大きな政府であっても財政赤字は少なくなっています。
北欧諸国に比較すると公務員数の比率が少ないながら、戦後民主改革によって獲得された結果的客観的評価システムを、温存されたグループ主義によってその機能が落とされていった日本が先進国随一の財政赤字国になっていることを見ても分かります。
北一輝の改造法案における経済構造変革に関する基本構想は、国有化至上のソ連型社会主義ではなく、私企業至上主義の資本主義でもない、独自の混合経済体制の構築でした。
大資本を要し、強力な対外競争力を必要とする分野は大資本の国家的統一を行うと同時に、私企業の必要性を認め、私有財産制に基づく自由主義的な機材制度を基本とし、小資本による私人経済が予見できる将来において経済活動の大部分を占めるだろうという現実的判断の下、従来民間の参入を排除していた産業分野を民営化するというものです。
つまり、具体的に言うと、国鉄の独占ではなく、支線鉄道の民営解放、塩と煙草の専売制度廃止などです。
しかし、積極的な私企業・民営肯定論だけでは経済活動における財閥の比重が増大するにつれて、独占資本と大地主の連合が政党を支配し、官僚を取り込み、軍部を動かし、帝国主義的な侵略を行っている状況を打破することはできません。
北は財閥の権力を制限する為に、法案では、私的企業の資本金上限額を一千万円としますが、現代で換算すると三百億円となり、当時資本金一千万円の企業と言えば鴻池銀行、伊藤商事などのかなりの大会社であり、大規模な私企業の活動が認められている形となっていました。
そして何より、『国民主権』、『言論の自由』、『基本的人権の尊重』、『治安維持法の廃止』、『普通選挙』、『貴族院・枢密院の廃止』などによって、安定した民主主義の道筋が根付けられているため、政府に対する民主的コントロールつまり、結果的客観的評価システムが機能する方向性となります。
北の改造法案の内容は、作家の三島由紀夫(皇国主義者である三島自身は戦後民主主義や北の思想には批判的でしたが)が述べている様に、日本国憲法、戦後民主改革によってほぼ実現されたと言えます。
上記内容(『』の中)や、国民の天皇、華族制の禁止、国民自由の回復を声高に歌い、国民の自由を拘束する新聞紙条例や出版法の廃止を主張していますが、これらは全て、日本国憲法によって実現されたもので、私有財産の限度も、日本国民一人の所有するべき財産の限度を3百万円、現代の百億円と規定されていますが、実質的には戦後の累進課税・相続税その他の負担が自ずから改造法案の目的をほぼ実現してしまっています。
また、大資本の国家統一についても、戦後の護送船団方式によって同様のことが言えます。
逆に言えば、北の改造法案が日本の戦後民主時代を創り上げたと言えます。
改造法案が日本国憲法の雛形となり、その思想に影響を受けた人々が国内外問わず、戦後日本の政治の舵取りに深く関与したことを考慮すると判ります。
しかし、戦前の実権を握っていたグループ主義の根本部分が温存されたためために、戦後民主改革によって一度は大きく解除されたグループ主義が、少しずつ再構築されていきことにより、戦後民主制度が歪められ、グループ主義の暴走が再び進行していきます。
彼らが完全に実権を握っていた戦前の憲政の常道期においての民主主義といわれたものの実態は、首相を選出する権限は宮中にあり、歴代総理大臣は二人を除けば、衆議院議員でなく、国民代表とはとても言えない貴族院議員であり、政党内閣の最高指導者の半数以上は、自らに対する選挙の洗礼を恐れなくていい人々でありました。
また政友会は三井財閥、民政党は三菱財閥など政党と財閥の結託や腐敗が著しく、また選挙の度に政権党がかつという不可思議な現象が常態化しました。
つまり、本来は政党間の政権交代は総選挙という国民の審判を通じて行われるべきであるのが、野党の政党は官僚・枢密院・財閥・軍部などの勢力と結んで倒閣を目指し、それを果たした野党の政党が議会の少数派のままで組閣し、与党という有利な条件の下で総選挙に勝って第一党に躍進するという形式が政権交代の基本的形式となっていました。
政権交代の度に百人単位で官僚が入れ替わり、政権党系の府県知事や警察幹部などが配置され、選挙干渉を行うというものです。
この為、国内外問題が山積みの状態なのに政党においては党利党略が最優先され、抗争だけが進行し、問題解決はほとんどされない状況で、国民の民主政治への不信感の延長線からの軍部台頭における統制経済下などでは、安定した民主政治から派生する結果的客観的評価システムの裏打ちは望めるはずがありません。
それに対して、北の目指した政府における経済・資本における規制などは、結果的客観的評価システムの機能の裏打ちを伴うものである点で全く質的に異なるものと言えます。
この様に、北の方向性は、戦後民主主義の雛形である以上、当然その方向性とほぼ同方向であるのを無理やり、戦前のファシストと類似点をピックアップし、そのレッテルが貼られてしまいます。
その類似点も質的に別物であり、この戦前は民主主義者として非難し、戦後はファシストとして非難する矛盾極まりない論理が常道として通ってしまうということは、王安石の例を見ても、日本の戦前から続くグループ主義は戦後改革によって弱められ、メンバーがいくらか変わったにしても根強く、実権を保持していることが分かります。
北の再評価がされるのは、王安石の再評価と同様に体制の大きな変化と共に実行されるであろうことが予測できます。(詳しくはこちら)
つまり、官僚、縁故主義のグループ主義が結果的客観的評価システムによって、しっかり制御されるシステムが根付く時であると思われます。