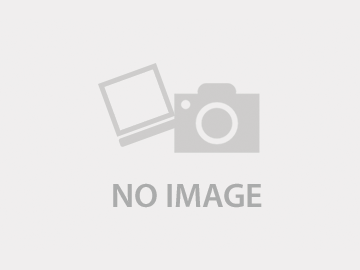自省録はローマ皇帝で五賢帝の一人、マルクス・アウレリウス・アントニヌスが書いた哲学書です。
自分宛てに書き続けた短い散文の集積であり、内容はローマ帝国の当時の状況や職務上の記録などはほとんどなく、彼自身の哲学的思索に限定されています。
彼の実施した政策は、貧民階級の子供に対する慈善政策を進め、言論の自由を保障し、喜劇作家による皇帝の揶揄も許容。
孤児や少年少女の保護、解放奴隷についての法律、市議会議員選出法の改革など現代にも稀だと思われるような、理想的な政策が並びます。
正に名君と言っていい存在だと思います。😀
しかし、この自省録を読んでいくにおいて、第5章第6節の内容に少し引っかかるものを感じました。
【彼は葡萄の房をつけた葡萄の樹に似ている。葡萄の樹はひとたび自分の実を結んでしまえば、それ以上なんら求むるところはない。あたかも馳場を去った馬のごとく 、獲物を追い終せた犬のごとく、また蜜をつくり終えた蜜蜂のように。であるから人間も誰かによくしてやったら、〔それから利益をえようとせず〕別の行動に移るのである。あたかも葡萄の樹が、時が来れば新に房をつけるように。】
この直前で、マルクス・アウレリウスは三様の人々を挙げています。善事を施し見返りを求める者、見返りを求めないが心で密かに相手を負債者のように考える者、そして自分のしたことを意識しない者である。上にあげた比喩で葡萄の樹に似ているとされたのは、3つ目のような人々です。
これはGIVE&TAKE(詳しくはこちらをクリック)でいうところの何も考えずにただ単純に『GIVE』してしまい、搾取されてしまっているだけの状態になってしまう奪われるギバーに近いのではないのかとふと思いました。🙄
つまり、自己犠牲のギバーです。
成功するギバーでは、『GIVE』は計画的、自主的にされ、相手に『GIVE』した時、相手は助けられた実感があり、その上で、自分にもメリットがあるつまり、WinWinの関係性となっていることが必要です。
マルクス・アウレリウスの寛容さは有名です。
ゲルマンの部族とは晩年まで講和をしては破られ、また協定を結んでは破られるというイタチごっこが続きます。
重ねてルキウス帝の下でパルティア戦争を戦ったシリア総督アウィディウス・カシウスが反乱を起こし皇帝を僭称します。 この反乱劇はマルクス帝が死亡したというデマを信じたカシウスの勇み足で起きたもので、ローマ兵によって鎮圧されましたが、事後の処分は非常に穏便なものになりました。
この自己犠牲のギバー的寛容さが、彼の最大の汚点といわれる後継者問題(後継指名した息子のコンモドゥスが暴政を行う。しかもそのきっかけをつくったのが、娘のルキッラ)に繋がったような気がします。😥
生まれついてから、与えられ過ぎた者はどうしても堕落するといわれます。
名君といわれる者のほとんどが逆境もしくは庶民の中で育っている(中国歴代最高の名君とされる清の康熙帝、日本江戸幕府中興の祖といわれる徳川吉宗、朝鮮王朝の正祖など)のを見てもわかります。
マルクス・アウレリウスの長所である寛容さ・優しさ・ギバー的要素がそのまま欠点となってしまったということでしょうか・・・・・