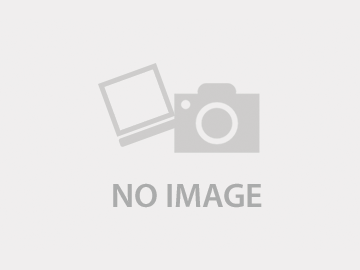②のアプローチ(個人的な自分自身の周囲の他の人々との関係を良好にしていくということ)と③のアプローチ(国・世界などの大きな公的社会環境をより良いものに改善していくということ)は相反するということは別記事で書かせていただいています。(詳しくはこちら)
また、自己啓発的なものは基本②のアプローチであることも別記事で書かせていただいています。(詳しくはこちら)
②のアプローチと③のアプローチの対比として、ある公的組織の人事権を持つⒶ(②のアプローチで人事を行う)とⒷ(③のアプローチ人事を行う)で表現してみます。
Ⓐは自分の周囲に拘り、能力よりも自分との個人的関係の距離や利益を基準に人事を行います。
Ⓑは公平に分け隔てなく、自分の周囲(家族・一族・派閥など自分の所属するグループもしくは知己など)に拘らず、能力を基準に人事を行います。
前者は公的組織内部に次々と自らの身内を採用し、グループの結束力で組織内の発言権を増していき、出世していきます。
後者は公的組織にとって、勿論のことプラスの行動を取っているのですが、孤立しやすくなり、個ではどんなに優秀であったとしても、集団に対抗は難しく、失脚していきます。
これにまさに当て嵌まるのが、儒教と法家の対比です。
儒家は 家族血族主義でて徳治・人治裁量主義、身分制度秩序の肯定となります。(②のアプローチ)
法家は『信賞必罰』を旨とした実力主義、血縁社会よりも社会的公正を優先する法治裁量主義となります。(③のアプローチ)
前者の場合、人の裁量・主観的な判断で物事が決められて行きます。
家族血縁主義、身分制度秩序の肯定も相まって、一部の血縁、一族が閨閥を形成し、利権を独占する特権階級を生み出しやすくなります。
一部の閨閥グループが利権を得ている状態は、客観的基準があれば、その方向性で人は努力しますが、それがなく主観的な徳があるなしで、しかも実質血縁で利権が分配されている状態であれば、他の一族グループにとって非常に不公平で不公正なシステムに映ります。
一度構築された身分制度秩序が肯定されても、客観的に他の多数のグループにとって不公平・不公正感がある限り、利権・特権階級を得るためのグループ間の争いは激化して行きます。
後者の場合、法という客観的基準によって物事が決められて行きます。
前者と違い癒着・不正が起こりにくく、特定のグループに力が集中しにくくなり、公(おおやけ)、国全体が豊かになる傾向があります。
秦の法治主義路線は百年以上前の商鞅の時代から、他の国々に見られない例外的に長期間続いた状態でした。
それにより、秦国は国力を高め、中華を統一することができました。
法家の呉起が、秦の同格の大国であった楚において悼王の信頼の下、改革を担いましたが、悼王死去後すぐに呉起は失脚し、その改革も続かなかったのに対して、秦においては、同じように、考公の信頼の下で、商鞅が法家主義的政策で改革を断行し、考公亡き後、すぐに失脚しましたが、その後もその政策は引き継がれました。
それが秦が中華を統一し、楚ができなかった大きな理由です。
秦の中華統一後、統一に伴う度重なった土木工事による民衆の疲弊と滅ぼされた国々の人民の反発によるところと後を継いだ二世皇帝が暗愚であったことから秦は滅亡します。
これは後の世において、同様に戦国の世を統一しながら短期間に滅亡した隋と共通するところです。
その後、秦の法制度を受け継いだ漢は統一国家を存続させていきます。
文帝・景帝の時代では食料が食べ切れずに倉庫で腐敗したり、銭の間に通す紐が腐って勘定ができなくなったなどの逸話も残されています。
ただ、武帝の時代に儒教を国教とし、郷挙里選の法と呼ばれる官史任用法が採用されました。
これは各地方郷理の有力者とその地方の太守が話し合って当地の才能のある人物を推挙するもので、特に儒教の教養を身につけた人物が登用されました。
儒教の考え方は祖先や家族愛を大切にし、礼や道徳を尊ぶ貴重な要素が多く含まれています。
しかし、それらはミクロ的・私的な環境下で重要視すべきであり、古代周の時代の様に公の単位がミクロ的な場合は別にして、時代が進み、マクロ的・公的になった環境下でそれを重要視することは極めて適さない形となります。
同じ諸子百家の一つの墨家から儒教の家族愛は特定の集団に対する愛、差別愛、偏愛と批判されています。
個々の家族内のミクロ的なレベルではともかく、国家レベルでのマクロ的にこれが実践されると閨閥主義が蔓延り、先天的な階級社会が原則となり、公平性を欠く社会になってしまう傾向になります。
また儒教の考え方である徳治主義は人治裁量主義であり、法家が社会的公正を理念とするのに対し、仁を施すと称する恣意の裁量政治が同じ閨閥や派閥の不正を裁かず、利権と最も深く結びついている官史任用に際しても、徳や才は名ばかりで人情採用が横行し、当然その結果、利権における癒着・賄賂が蔓延り、利権や特権を得るための閨閥や派閥間での争いが激化してしまいます。
実際、武帝の前半の治世は文景の治による蓄積によって繁栄しますが、後半は不正や賄賂、反乱、盗賊の横行が各地で凄まじく蔓延し、側近の職権乱用が原因とする皇太子の反乱や巫蠱の罪など冤罪で多くの者が裁かれたり、混乱を極めます。
その後、混乱した状態を収拾したのが漢王朝の中興の祖といわれた宣帝です。
宣帝は信賞必罰をモットーとした法家主義的政治信条に則り、法政通を官僚に起用し、政策に疎い儒者達を政治の中枢から遠ざけ、弱体化していた漢の国勢を復興させることに成功します。
しかし、その後、儒教に傾倒し過ぎるために皇太子時代に宣帝から廃位を一時検討された元帝が結局、即位します。
元帝は儒教に傾倒し、現実離れした政策を実施し、財政は悪化、国政を混乱させます。
宣帝により中興された国勢は再び衰え、元帝の皇后一族からでた王莽の簒奪、前漢滅亡の端緒を開くことになります。
その後、漢を乗っ取り、新を建国した王莽の王朝も同様いやそれ以上に儒教帝国と呼ばれる位、儒教一辺倒の国家になります。
現実性に欠如した各種政策は短期間で破綻、貨幣の流通や経済活動を停止したために民衆の生活は前漢末以上に困窮し、民衆の反乱が続発し、十五年という短期間に新王朝は滅んでしまいます。
その後、混乱を収拾した劉秀が後漢を興し、光武帝となります。
光武帝は法家政策を採り、宣帝を高く評価し、儒教は重んじながらも政治は法家・法治主義で行いました。
疲弊した民を救うために、度々の奴隷解放令を出すとともに、人身売買を厳しく規制し、奴婢と良民の刑法上の平等を宣告し、豪族の跋扈する郡には酷使と呼ばれる人物を太守に起用し、横暴な豪族を制圧し、犯罪数が前漢時代の五分の一に減少しました。
また、税を三分の一に、役所を統廃合し、冗官の削減をし、人民の負担の緩和を図りました。
その後を継いだ明帝も法家と儒家のハイブリッド的な政治を行い、二代に渡り、後漢期においては安定した全盛期を現出しました。
しかし、その後は王莽の治下で儒学の校舎を全国に設置して、奨励させた影響から後漢中期には儒教を学ぶ者が急増し、三代章帝の時代からは完全な儒教国家となってしまいます。
そして、外戚と宦官勢力が政争を繰り広げ、後漢は衰退していきます。
法家の韓非子(クリックするとリンクします)が述べてている通り、法の力によって君子の下で正しい政治を実現しようとする者、これを法術の士とし、 私利を図り王朝を害している者を当途の人とすると、両者は相容れない敵同士となりますが、当途の人は君主に気に入られており、君子と顔なじみであり、耳に気分の良いことだけを言い、身分 が高く、子分を多く従えている場合が多く、法術の士は君主の覚えがなくて、新参者で、耳の痛いことを口にし、身分が低く、味方のいない場合が多いために、法術の士が当途の人に勝てる見込みは全く薄く、この力の差によって、法術の士は身の危険に曝され、当途の人は何か罪をでっち上げられるのであるならば、刑罰を利用して殺そうとし、それれにより当途の人とそれに従って利益を得ようとする者たちが好き勝手に振る舞い、有能な者や潔白な者が彼らに阻まれ、政治が腐ってしまう傾向が極めて強くなります。
法家の特質として、公的客観性を保つために、私的関係を排し、制御する為に集団から距離を保ち傾向にあり、周囲からは見れば場が薄いとも受け止められ、登用されたり、実権を握るのは歴史的に見ると例外的な出来事となってしまっています。
実際、法家の人は身分が低い者もしくは不遇であることが多く、宣帝や光武帝などの法家を重視した皇帝も出生時には本来ならば皇帝になれる身分・地位ではないか、政(後の始皇帝)の様に待遇が悪い環境下であることも共通しています。
生まれながらにして、皇帝を継ぐ程に身分が高く、待遇が良ければ、自然の流れで既存の身分制度秩序を肯定する儒家に靡いてしまうのは当然の理かもしれません。
国々が乱立する中、生存競争のために、富国強兵が切実である状態で、開明的な君主により、有能の士を募っている中、信頼を勝ち取るか、幸運にも身分や待遇の低い状態から皇帝として昇り詰めるしか法家が政治の実権を握るのは難しくなります。
開明的な君主の信頼を勝ち取っても二代続いて英君 は続かず、大抵は 悲惨な末路を歩むことになります。
また幸運にも低い立場から皇帝になったとしても、次の跡継ぎは身分・待遇が高い立場であり、代を重ねるにつれて、儒家に傾いて行きます。
つまり、法家(③のアプローチ)が実権を握れるのは例外的な場合になり、原則的に儒家(②のアプローチ)が主となり、少数のグループによる主観的な政治が行われ、公(おおやけ)、国の利益に沿った客観的な基準は歪められ、公(おおやけ)主義というよりも、それぞれのグループの利益・特権を求めて争うグループ主義的な時代となります。
②のアプローチである人を動かすための弁論術(直接民主政治における議会に影響力を及ぼすため)が極めて重視されたギリシャの民主制では客観性よりも主観性が先行し、好戦的なデマゴーゴスが民衆を扇動する典型的な衆愚政治により国家を衰退させていきました。
自己啓発的な要素を多く含み、ヘレニズム世界・ローマ帝国において知的エリート階層の主流派の哲学となったストア派哲学においても、それを政治に反映させたローマの最後の五賢帝マルクス・アウレリウス後のローマでは自身の実子で後継者であるコンモドゥスの暴政(コンモドゥス帝が暴君となるきっかけをつくったのも自身の実子でコンモドゥス帝の姉であるルキッラによるコンモドゥス帝の暗殺未遂事件)により衰退していきます。
またマルクス・アウレリウスと同様にローマ三賢人の一人であり、ストア派哲学者であったセネカが、幼少期から家庭教師となり、また治世においてはブレーンとして支えたローマ皇帝ネロも暴君となり、ローマを混乱期に導いています。
さらに、アレクサンドロスの後継者のほぼ全員が自らをストア主義者だと認識していましたが、彼らはアレクサンドロス亡き後に壮絶なその後継者争いを展開させています。
これらの上記事象を見ると、②のアプローチが先行し過ぎてしまうと公的社会環境においては逆に作用してしまうことが分かります。
ただ、誤解をしてほしくないことは、決して②のアプローチが不必要なことではなく、それだけ先行してしまうと片車輪だけ大きくなり、その状態で走ってしまうとより早くなるどころか、バランス的に悪くなり、事故ってしまうリスクだけが高くなるということです。
③のアプローチそして②のアプローチと③のアプローチをリンクさせる客観的評価システムがあることによって初めて両車輪で安全に早く、幸福な社会構築に人々は進めるのです。
言い換えると、必須アミノ酸におけるアミノ酸の桶の理論に近いものがあります。
九種類のうち、一番含有量の少ないアミノ酸を一番背の低い桶板に例えると、いくら満杯にしようとしても、そこから水が流れてしまう。
つまり、吸収されずに排出するために、エネルギーや栄養素を無駄に浪費し、逆効果になるというものです。
必要量に対して充足率の最も低いアミノ酸を制限必須アミノ酸と言います。
公的社会の利益、公益において最も制限必須アミノ酸になりやすいのが、客観的評価システムと言えます。
②のアプローチもの必須アミノ酸の一つであっても、その時の制限必須アミノ酸でなければ、いくら摂取しても排出され、摂取・排出の際のエネルギーが浪費されるだけのマイナスの行為になってしまうということです。
制限必須アミノ酸が充足されてはじめてそうでない必須アミノ酸も有効に摂取され、本来的にはそれぞれが対立するのではなく、相互補完的に吸収されるのです。
2